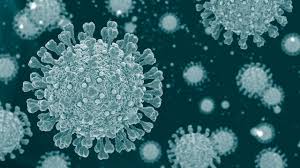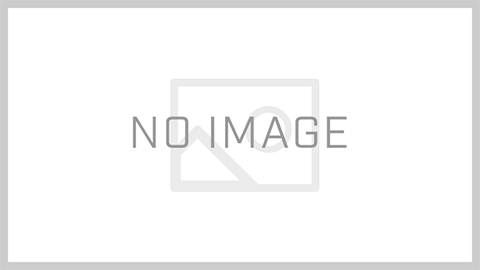全国の国立大学病院が令和7年度に400億円超の赤字見込みを発表し、「過去最大の危機」との強い危機感が示されました。 これは単なる財務問題ではなく、医療・教育・研究という三層構造が同時に崩れかけている制度的危機です。
🧭 構造分析:三層の制度疲労
① 医療:診療の質と設備更新の限界
- 筑波大学附属病院では開院以来最大の赤字(28億円)
- 医療機器の98%が更新できず、診療の質に影響
- → 高度医療を担う大学病院が、設備老朽化と人件費高騰で収支崩壊
② 教育:医師養成機能の低下
- 「立派な医学部の学生を教育できない」「医師を育てられない」
- → 教育機材・人材・環境の維持が困難に
- → 医療人材の供給構造が制度的に崩れ始めている
③ 研究:先端医療の停滞
- 医療機器の更新不能 → 臨床研究の停滞
- → 日本の医療技術革新が止まりかねない構造的リスク
💬 安心設計の崩壊
- 「医療はとても大事なので、不安を感じる」
- 「看護師・先生が少なくなっていると。困る」
- 「継続して診てもらえることが大切」
→ これは「医療の質」ではなく、生活者の“安心設計”が崩れているという感情構造です。
⚖️ 制度の限界:診療報酬と財政支援のジレンマ
- 病院長らは診療報酬の引き上げや財政支援を要望
- → しかし、保険料や税金の負担増には限界
- → 制度の持続可能性と生活者負担のバランスが崩れている
🧠 “治す力”ではなく“支える構造”で
この問題は、「病院が赤字」ではなく、制度が“医療・教育・研究”を支える構造として機能しているかどうかが問われています。
- 医療制度は“治療”であると同時に、“社会の安心設計”
- 教育制度は“育成”であると同時に、“未来の医療の担保”
- → 制度は「支える力」として再設計されるべき
つまり、医療制度は“治す力”ではなく“支える構造”であるべきなのです。
🗂️ タグ
#国立大学病院と制度疲労の三層構造#医療機器更新不能と診療の質低下#医師養成と教育機能の崩壊#生活者の安心設計と医療信頼の断絶#診療報酬と財政支援の制度ジレンマ