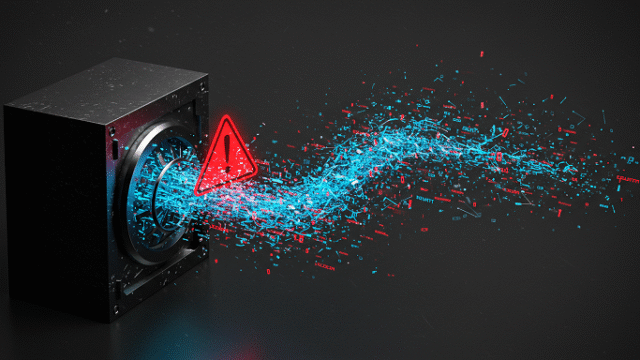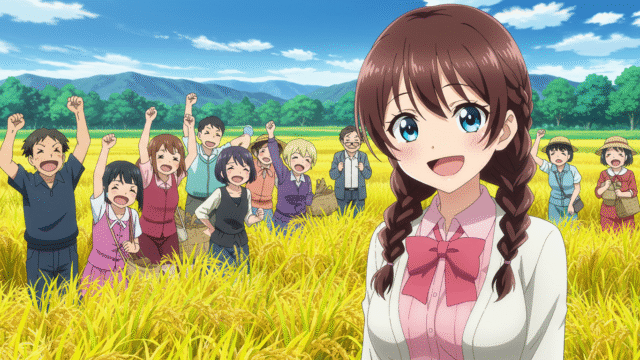厚生労働省が示した新たな方針が、精神保健医療のあり方に静かに大きな波紋を広げています。 それは、精神科病院での入院対象から「強度行動障害の人など治療効果の見込めない人」を外すというもの。 今後は、急性期の患者や早期退院を目指す人を中心に入院医療を絞り込み、慢性期の支援は地域へ──という構造転換が進められます。

強度行動障害とは、知的障害や自閉症の人の一部に見られる自傷、こだわり、睡眠の乱れ、異食など、特別な配慮が必要な状態。 これまで、障害者支援施設での受け入れが難しく、精神科病院に入院せざるを得なかったケースも多くありました。 しかし、厚労省は「入院医療中心から脱却する」と明言。 代わりに、地域で支える体制として「機能強化型の訪問看護事業所」の創設を打ち出しました。
この訪問看護事業所には、24時間対応や医療・福祉の連携、短期入所との連携、身体合併症への支援など、複数の役割が求められています。 委員会では大きな異論は出なかったものの、「医療色が強くなりすぎることへの懸念」や「服薬による行動抑制への批判」など、ケアの質に関する議論も続いています。

これは「施設から地域へ」「隔離から共生へ」という福祉の流れの中で、“誰が、どこで、どう支えるか”を再設計するフェーズ。 精神科病床の削減という現実を前に、訪問看護が“新しい拠点”になる可能性を秘めています。
ただし、制度だけでは支えきれません。 現場の人材、地域の理解、そして何より「本人の尊厳を守るケア」が必要です。 障害福祉と医療の境界を越えて、“暮らしの中で支える”という発想が問われているのだと思います。