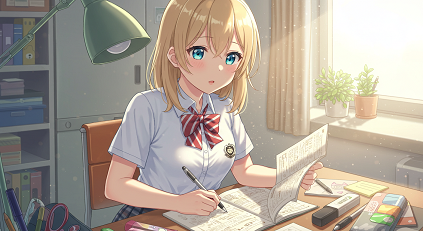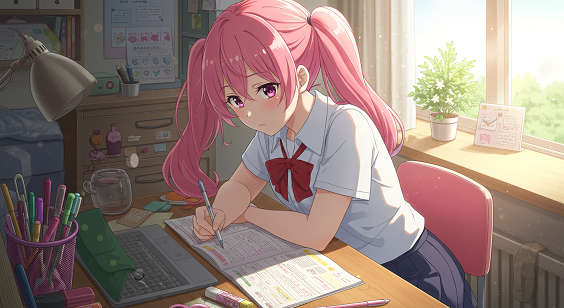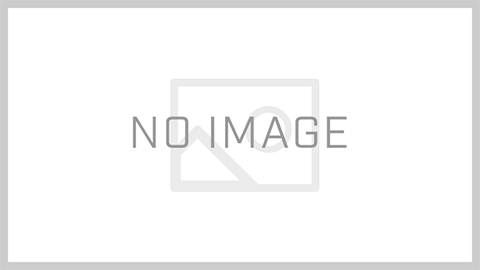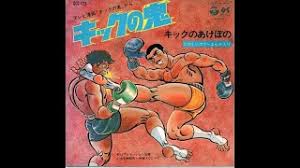小学生低学年向けに書いた『走れメロス』の読書感想文(約500文字)
ぼくは『走れメロス』を読んで、メロスの友だちを思う気もちに心をうたれました。メロスは王さまにうそつきだとおこって、つかまってしまいます。でも、妹のけっこんしきを見たいからと、いったん町にもどります。そして、やくそくどおりにまた王さまのところへもどってきました。
ぼくは、「なんでにげなかったのかな?」と思いました。にげればじゆうになれるのに、メロスは友だちとのやくそくをまもるために、つかまることをえらびました。とてもゆうきがあると思いました。
メロスがつかれながらも走っているところでは、「がんばれ!」と心の中でおうえんしました。雨がふっても、山をこえても、あきらめないメロスのすがたに、ぼくもがんばろうと思いました。
この本を読んで、ぼくも友だちとのやくそくを大切にしたいと思いました。そして、つらいことがあっても、メロスみたいにあきらめずにがんばりたいです。
小学生低学年向けに書いた『走れメロス』の読書感想文(約1000文字)
ぼくは『走れメロス』を読んで、とても心がドキドキしました。メロスは、友だちとのやくそくをまもるために、どんなにたいへんでもあきらめずに走りつづけました。そのすがたがかっこよくて、ぼくもこんな人になりたいと思いました。
メロスは、王さまが人をしんじないことにおこって、つかまってしまいます。でも、妹のけっこんしきを見たいからと、王さまに「三日後にかならずもどってくる」と言って、町にもどります。そのかわりに、友だちのセリヌンティウスが人しちになって、メロスがもどらなかったら、かわりにころされてしまうのです。
ぼくは、「そんなことまでして、けっこんしきを見たいのかな?」と思いました。でも、メロスは妹のしあわせをねがっていたし、友だちとのやくそくをまもるために、ぜったいにまにあわせようとがんばります。山をこえたり、川をわたったり、どろだらけになっても、メロスは走りつづけました。
とちゅうで、メロスはつかれてたおれそうになります。でも、「友だちをうらぎってはいけない」と思って、また立ちあがります。そのとき、ぼくは「がんばれメロス!」と心の中でおうえんしました。メロスの気もちがまっすぐで、うそがなくて、すごいと思いました。
さいごに、メロスはまにあって、王さまの前で「やくそくをまもったぞ!」と言います。セリヌンティウスもメロスをしんじてまっていてくれました。ふたりがかたく手をにぎりあうところは、とても感動しました。王さまも、ふたりのしんらいを見て、心がかわっていきます。
この本を読んで、ぼくは「やくそくをまもること」「友だちをしんじること」がどれだけ大切かを知りました。ぼくも、友だちとのやくそくを大事にして、うそをつかない人になりたいです。そして、つらいことがあっても、メロスみたいにがんばってのりこえたいと思いました。
森絵都さんの小説『カラフル』を読んだあとの読書感想文(約1000文字)です。中学生〜高校生向け
ぼくは『カラフル』を読んで、「生きることの意味」について深く考えさせられました。物語は、死んだはずの“ぼく”が、天使に「抽選に当たった」と言われて、もう一度人生をやり直すチャンスをもらうところから始まります。しかも、その人生は他人の体を借りて生きるという、少し不思議な設定です。
最初、主人公は人生に対して冷めた目を持っていて、周囲の人間関係にも興味を持てず、どこか投げやりな態度で過ごしています。でも、家族や友人、学校での出来事を通して、少しずつ「この世界には色がある」と気づいていきます。特に、家族の秘密や友人の悩みを知ったとき、主人公は「自分だけが苦しいわけじゃない」と感じ始めます。
ぼくが心に残ったのは、「人は誰でも、見えないところで悩みながら生きている」ということです。主人公が他人の体を借りて生活することで、他人の視点から自分を見つめ直すことができたように、ぼくもこの本を読んで、自分のまわりの人たちの気持ちをもっと考えてみようと思いました。
また、タイトルの『カラフル』には、「人生にはいろんな色がある」という意味が込められているように感じました。楽しいこと、悲しいこと、苦しいこと、うれしいこと——それら全部が混ざって、ひとつの人生になる。主人公が最後に「生きてみよう」と思えたのは、そうした色の存在に気づいたからだと思います。
この本を読んで、ぼくは「生きることは簡単じゃないけれど、無意味ではない」と思えるようになりました。もし、つらいことがあっても、それは人生の一部であり、そこから何かを学ぶことができるかもしれない。そして、自分のことだけでなく、まわりの人の気持ちにも目を向けることで、世界は少しずつ優しくなるのかもしれません。
『カラフル』は、ぼくにとって「生きることの意味」を考えるきっかけをくれた大切な一冊です。これからも、いろんな色を感じながら、自分の人生を大切にしていきたいと思います。
森絵都さんの小説『カラフル』を読んだあとの読書感想文(約1500文字)です。中学生〜高校生向け
森絵都さんの『カラフル』を読んで、私は「生きることの意味」や「人とのつながり」について深く考えさせられた。物語は、死んだはずの“ぼく”が天使に「抽選に当たった」と告げられ、再び人生をやり直すチャンスを与えられるという不思議な設定から始まる。しかも、その人生は他人の体を借りて生きるという条件付きで、主人公は中学三年生の小林真の体に“ホームステイ”することになる。
最初の“ぼく”は、人生に対して冷めた目を持ち、周囲の人間関係にも無関心で、どこか諦めたような態度で日々を過ごしている。だが、真の家族や友人、学校での出来事を通して、少しずつ「この世界には色がある」と気づいていく。特に、家族の秘密や友人の悩みを知ったとき、主人公は「自分だけが苦しいわけじゃない」と感じ始める。人は誰でも、見えないところで悩みながら生きているのだ。
印象的だったのは、真の母親が実は不倫をしていたという事実を知ったときの主人公の反応だ。最初は怒りや嫌悪を感じるが、次第に「母親もまた孤独で、誰かに寄りかかりたかったのかもしれない」と理解しようとする姿勢に変わっていく。この変化は、主人公が他人の視点から物事を見られるようになった証であり、彼の成長を象徴しているように思えた。
また、親友のヒロとの関係も重要な要素だ。ヒロは明るくて人気者だが、実は家庭に問題を抱えており、心の中では孤独を感じている。主人公はヒロの弱さに気づき、彼を支えようとすることで、自分自身も少しずつ変わっていく。人との関わりの中で、自分の存在が誰かの支えになることを知ったとき、主人公は初めて「生きてみよう」と思えるようになる。
タイトルの『カラフル』には、「人生にはいろんな色がある」という意味が込められているように感じた。楽しいこと、悲しいこと、苦しいこと、うれしいこと——それら全部が混ざって、ひとつの人生になる。主人公が最後に「生きてみよう」と決意する場面では、彼がようやくその“色”の存在に気づき、自分の人生を受け入れる準備ができたことが伝わってくる。
この作品を通して、私は「生きることは簡単じゃないけれど、無意味ではない」と思えるようになった。もし、つらいことがあっても、それは人生の一部であり、そこから何かを学ぶことができる。そして、自分のことだけでなく、まわりの人の気持ちにも目を向けることで、世界は少しずつ優しくなるのかもしれない。
『カラフル』は、私にとって「生きることの意味」を考えるきっかけをくれた大切な一冊だ。これからも、いろんな色を感じながら、自分の人生を大切にしていきたいと思う。そして、誰かの心に寄り添えるような存在になれたら——それこそが、私にとっての“カラフル”な生き方なのかもしれない。