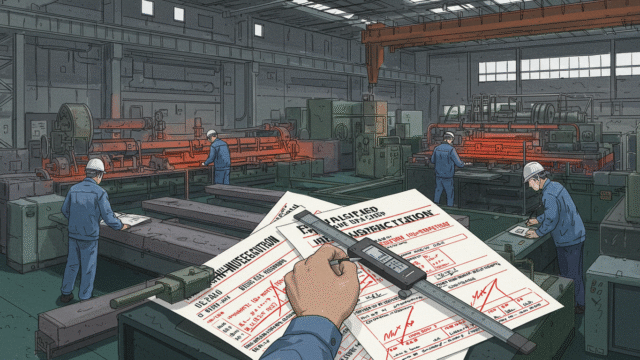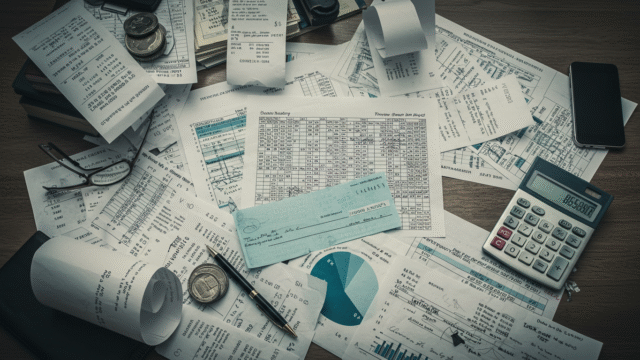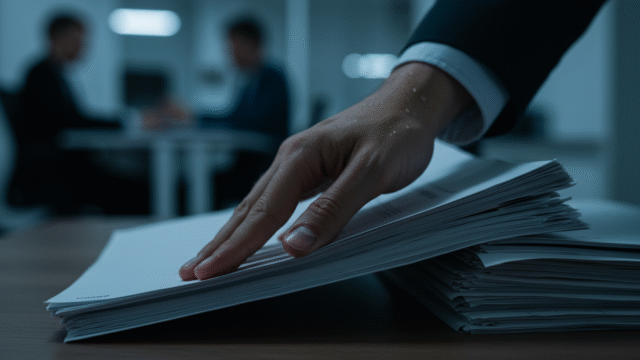🕰️プロローグ:黒豆プリンの賞味期限
2007年秋、福岡市の百貨店で販売されていた「黒豆プリン」。 そのラベルは、毎日張り替えられていた。 賞味期限切れの商品が、何事もなかったかのように並べられていた。
それは、船場吉兆による食品偽装の始まりだった。 “料亭文化の象徴”が、“食の信頼”を裏切った瞬間だった。
🧠第1章:偽装の手口と広がり
船場吉兆が行っていた偽装は、単なる一品の誤表示ではなかった。 その手口は多岐にわたり、組織的かつ常習的だった。
主な偽装内容:
- 賞味・消費期限の改ざん → ラベルを張り替えて期限切れ商品を販売
- 産地偽装 → 佐賀県産牛肉を「但馬牛」、ブロイラーを「地鶏」と表示
- 原材料偽装 → 鹿児島産牛肉を「三田牛」として販売
- 酒税法違反 → 無許可で梅酒を製造・提供
- 食べ残しの使い回し → 刺身のツマを洗って再利用、天ぷらを揚げ直して提供
偽装品目は最終的に44品目にのぼり、 “高級料亭”の看板は、信頼の象徴から欺瞞の象徴へと変わった。
🏛️第2章:経営陣の対応と“マザコン会見”
事件発覚後、船場吉兆は「現場のパート従業員が独断で行った」と主張。 だが、パート側は記者会見で「会社の指示だった」と反論。 その後、経営陣は偽装の責任を認めた。
記者会見の象徴的場面:
- 長男・湯木喜久郎取締役が母・佐知子取締役の指示を“オウム返し”
- 「頭が真っ白になっていて…」と母の言葉をそのまま引用
- 「手付かずのお料理」と呼び直すようマスコミに要望
この“マザコン会見”は、企業の説明責任のあり方を問い直す象徴となった。
📉第3章:ブランドの崩壊と廃業
事件後、百貨店は契約を解除し、看板を撤去。 農水省は「常習性あり」として行政処分を検討。 2008年5月、船場吉兆は廃業届を提出し、料亭の歴史に幕を下ろした。
🧩エピローグ:おもてなしの倫理とは何か?
船場吉兆は、創業者・湯木貞一が築いた“料亭文化”の象徴だった。 だが、その“おもてなし”は、期限切れのプリンと偽装された牛肉の上に成り立っていた。
この事件は、以下の問いを私たちに突きつける:
- ブランドとは、何を守るべきものか?
- 食の信頼は、誰がどう守るのか?
- 文化と倫理は、両立できるのか?