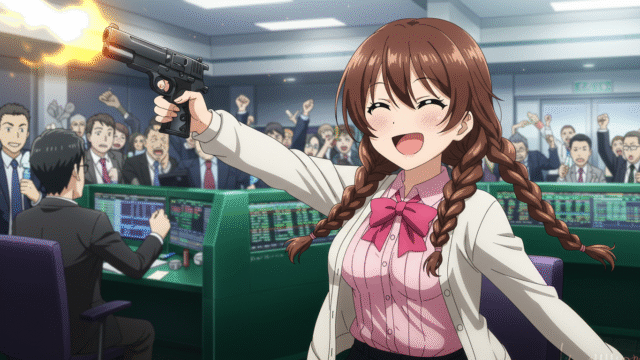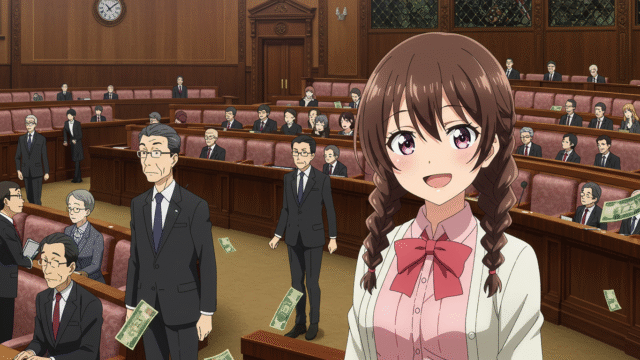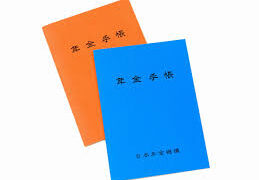皆さん、こんにちは!トランプ大統領の相互関税発表以降、金融市場は大きな動揺に見舞われていますね。一体この先、世界経済はどうなってしまうのでしょうか?この問題の深層と今後の展望について、じっくりと掘り下げていきたいと思います。
金融市場の過剰反応?冷静な視点の重要性
市場では、「日銀はもう利上げできない」「FRBの利下げは年内4回に増える」といった極端な見方も出ていますが、もっと冷静な視点が必要だと指摘します。
実体経済への影響は大きいものの限定的
確かに、関税が実体経済に与える打撃は無視できません。しかし、以下の2つの理由から、リーマンショックやコロナ禍のような絶望的な状況ではないと分析します。
- 人為的な問題であること: アメリカの景気悪化次第では、トランプ大統領が中間選挙前に方向転換する可能性があり、関税収入を減税の原資にするという戦略も考えられます。
- 過去の危機と比較して影響が小さいこと: ロックダウンや国際金融危機のような制御不能な事態ではなく、今回の関税による経済の落ち込みは限定的であり、金融危機も起きていません。
定量的な影響:世界のGDPを1%程度押し下げる可能性
試算によると、今回の関税による増税額は約110兆円。これは世界のGDPの約1%を毀損する程度であり、過去の経済危機と比較すると影響は小さいと言えます。さらに、増税分がアメリカの財政赤字縮小や減税の原資になる可能性も考慮に入れる必要があります。
アメリカと日本のGDP成長率への影響:ゼロ成長も視野に
試算では、トランプ大統領が発動したすべての関税によるGDP押し下げ効果は、アメリカで2.1%ポイント、日本で0.38%ポイント。これにより、両国ともにゼロ成長となる可能性も示唆されています。大幅なリセッションまではいかないものの、影響は決して小さくありません。
追加リスク:半導体、医薬品、報復関税の拡大
今後の追加リスクとしては、現在関税の対象外である半導体や医薬品、USMCA準拠品への拡大、そして中国に加えてEUなどの主要国・地域が報復関税を打ち出す可能性が挙げられます。ただし、これらのリスクが顕在化しても、経済押し下げのインパクトが現在の2倍になるほどではないと見ています。
金融市場の反応:株価下落と金利急落
相互関税発表後、日本やアメリカの株価は10%前後下落。日本企業が直面する追加関税コストが約8兆円弱と推計しており、株価の10〜20%程度の下げは理解できるとしています。
また、株価下落と同時に資金が国債に流れ、長期金利は急落。これに対し、市場は日米の中央銀行の金融政策の変化に注目していますが、市場の悲観的な見方は行き過ぎだと指摘します。
- FRBの利下げ: 関税の影響は一時的であり、初期反応としてインフレが強まる可能性があるため、年内4回の連続利下げは考えにくい。
- 日銀の利上げ: 今回のショックで利上げが後ずれする可能性はあるものの、「二度と利上げできない」という見方は極端。日本のインフレの主因は構造的な人手不足であり、大幅な景気後退がない限り、利下げは時期尚早。
中長期的な見通し:2つのシナリオ
トランプ大統領の関税政策の目的について、以下の2つのシナリオを提示します。
- 財源捻出シナリオ: 関税収入と連邦機関リストラによる財源を、選挙公約である減税の原資にするというもの。このシナリオが実現すれば、減税後にトランプ政権の関税への取り組みは落ち着き、来年以降は経済のプラス要因となる可能性があります。
- 「第2のプラザ合意」シナリオ: スティーブン・ミランCEA委員長の提唱する、ドル安誘導によるアメリカ製造業の復活を目指すというもの。アメリカ国債の外貨準備を持つ国に放出を促し、ドル安を誘導するもので、もし実行されれば日本経済に大きな打撃を与える可能性があります。
驚愕の「第2のプラザ合意」構想:世界を3分割!?
特に注目すべきは、2つ目のシナリオで提唱されている「第2のプラザ合意」構想です。ミラン氏の論文では、アメリカは同盟国を「アメリカの要求をのむ国」と「反発する国」、そして「敵対国や非同盟国」の3つのグループに分け、それぞれの対応を検討しているというのです。
西側同盟国に対しては、安全保障を盾にアメリカ国債の放出と100年債の購入を迫る可能性も示唆されており、日本も「アメリカの要求をのむ国」と見なされているかもしれません。
まとめ:2つのシナリオを念頭に今後の動向を注視
トランプ大統領の関税政策の目的が、単なる財源確保なのか、「第2のプラザ合意」に向けた布石なのか、現時点では判断がつきません。しかし、どちらのシナリオも今後の世界経済と金融市場に大きな影響を与える可能性があることは間違いありません。
私たちは、今後のアメリカの政策動向、そして世界の主要国の反応を注視していく必要があるでしょう。特に、「第2のプラザ合意」という驚愕の構想が現実味を帯びてくるのかどうか、しっかりと見守っていきたいと思います。