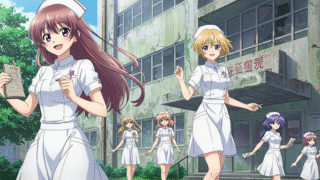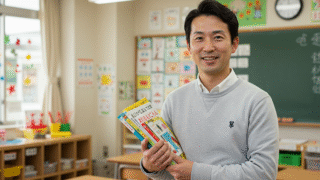化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐる冤罪事件で、警視庁公安部の捜査員2人が意図的に虚偽記載を行ったと、東京第6検察審査会が認定しました。 この議決は、不起訴処分(容疑不十分)を「不当」と断じた上で、虚偽公文書作成罪に該当すると明記。 制度の正義とは何か──その根幹が問われています。
🧭 事件の構造:立件ありきの“実験操作”
- 2017年:公安部が「噴霧乾燥器の不正輸出」容疑で捜査開始
- 立件の条件:装置が高温を維持し、殺菌可能であること
- → 民間企業の装置を借りて温度実験を複数回実施
- → 実験報告書に不利な温度データを記載せず
- → 温度計の設置経緯も事実と異なる記載
これは「立件ありき」の捜査が、制度の正義を歪めた構造的な逸脱です。
📉 検察審査会の認定:二つの“意図的なうそ”
① 温度データの省略 → 立件条件に達しない温度を記載しなかった → 「立件ありきの姿勢は許されない」と非難
② 温度計設置の虚偽記載 → 実際は捜査員が代表から借りて設置したのに、「代表が自発的に設置した」と記載 → 「積極的な虚偽記載」「供述は信用できない」と厳しく批判
→ 検察審は「共謀が成立し、虚偽公文書作成罪に該当」と結論付け、東京地検に再捜査と起訴の検討を要請。
💬 制度は“正義”ではなく“信頼”で動くべき
この事件は、「捜査の正当性」が「制度の信頼性」に直結することを示しています。
- 公文書は“証拠”であると同時に、“信頼の記録”
- 捜査は“真実の追求”であると同時に、“制度の誠実さの体現”
- → 虚偽記載は「立件のため」ではなく、「制度の崩壊」を意味する
つまり、制度は“正義”ではなく“信頼”で動くべきなのです。
🗂️ タグ
#冤罪と制度の信頼崩壊#虚偽記載と公文書の正当性#検察審査会と制度の再設計#立件ありきの捜査構造#生活者と司法制度の接点