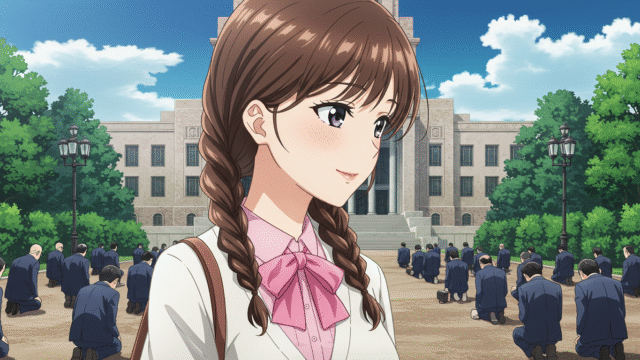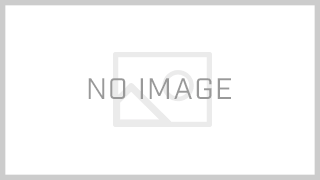2025年12月の導入を目指し、政府が検討を進める「日本版DBS」。 これは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度であり、イギリスのDisclosure and Barring Service(DBS)をモデルにしています。
でもこの制度、子どもの安全を守るための第一歩であると同時に、職業選択の自由や更生の機会との衝突という、制度設計上の難題も抱えています。
🧭 制度の仕組み:採用前に性犯罪歴を照会
- 採用候補者 → 教育委員会がこども家庭庁へ照会
- こども家庭庁 → 法務省に犯罪歴を確認
- 回答 → こども家庭庁 → 教育委員会へ通知
- 犯罪歴があれば本人に通知 → 応募辞退 or 訂正請求 → 不採用
この流れは、子どもと接する職業における“制度的フィルター”として機能します。 ただし、犯罪歴がない人でも潜在的な危険性がある場合は制度では拾えないという課題も。
📉 対象範囲の問題:義務と任意の“二層構造”
義務対象(照会必須):
- 幼稚園、保育所、認定こども園、小中高校、特別支援学校
- 児童福祉施設、放課後等デイサービスなど
任意対象(申請・認定制):
- 学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、学童保育
- ベビーシッター、認可外保育園、サークル活動など
→ 認定を受ければ安全性をアピールできるが、認定を受けない事業者にリスクが集中する可能性も。
💬 制度は“安全”と“自由”の間で揺れる
この制度は、「子どもの安全を守る」という明確な目的があります。 でもその一方で、以下のような制度的ジレンマも存在します:
- 職業選択の自由との衝突:「子どもに関わる仕事以外は自由に選べる」という反論もあるが、制度的には線引きが難しい
- 更生の機会の喪失:過去に罪を犯した人が、社会復帰の場を失う可能性
- 認定制度による市場淘汰:認定なしの事業者に子どもを通わせる家庭が減り、淘汰が進む可能性
つまり、制度は“安全の設計”であると同時に、“社会の再構築”でもあるのです。
🗂️ タグ
#日本版DBSと制度設計#子どもの安全と職業選択の自由#性犯罪再犯防止の制度化#認定制度と市場淘汰の構造#更生と社会復帰の交差点