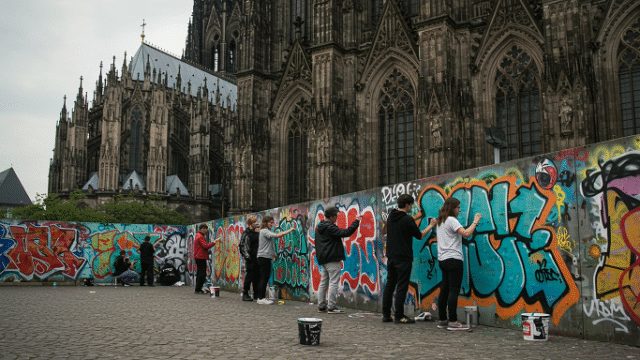数字が変わったのではなく、見方が変わった
2025年9月、政府の地震調査委員会は南海トラフ地震の発生確率を「80%程度」から「60〜90%程度以上」へと見直しました。さらに、別モデルによる「20〜50%」という数値も併記されるという異例の発表。
この変更は、「地震が起きにくくなった」わけでも、「急に危険度が上がった」わけでもありません。 科学的な不確実性を制度的にどう扱うか──その姿勢が変わったのです。
1. 南海トラフ地震とは何か:周期性と被害想定
南海トラフ地震は、静岡県から九州沖にかけての海溝沿いで発生する巨大地震。 過去には以下のような周期で発生しています:
- 慶長地震(1605年)→宝永地震(1707年):102年
- 宝永地震 → 安政地震(1854年):148年
- 安政地震 → 昭和地震(1944年・1946年):90〜92年
現在は昭和地震から約80年が経過しており、次の地震がいつ起きてもおかしくないとされています。 政府の被害想定では、最大で死者約29万8千人、津波被害は広範囲に及ぶとされています。
2. なぜ確率が「幅のある数値」に変わったのか
① 隆起量データの再評価
高知県室戸市・室津港の史料に基づく隆起量(地震による地盤の持ち上がり)を再検討。 これまでの固定値から、誤差を含む幅のある数値へ変更されました。
| 地震 | 旧データ | 新データ(平均±誤差) |
|---|---|---|
| 宝永地震 | 1.8m | 1.83m ± 0.51m |
| 安政地震 | 1.2m | 1.13m ± 0.52m |
| 昭和地震 | 1.15m | 1.02m ± 0.06m |
→ 隆起量が大きいほど次の地震までの間隔が長くなるという前提に基づき、誤差を含めた確率計算が必要になった
② 計算モデルの見直し
従来の「時間予測モデル」では、ひずみの蓄積は一定とされていました。 新たに採用された「すべり量依存BPTモデル」では、蓄積や解放にばらつきがあることを考慮。
→ より現実的なモデルだが、確率に幅が出る。これが「60〜90%程度以上」という表現の背景。
③ 他地域との整合性と“水増し”批判
南海トラフだけが突出して高い確率(80%)とされていたことに対し、「水増しでは?」という批判が国会でも取り上げられました。 そのため、他地域と同じBPTモデルによる「20〜50%」も併記することで、制度的公平性を担保。
3. 生活者にとっての意味:「数字の揺らぎ」は“備えの正当性”を示す
この確率の見直しは、生活者にとって「わかりづらい」ものかもしれません。 でも、重要なのは「数字の意味」ではなく、「数字が示す行動」です。
- 地震は「いずれ必ず起きるもの」
- 確率は「いつ起きるかはわからないが、備えるべきだという根拠」
- 不確実性を数値化することで、“備えの正当性”が制度的に裏付けられる
つまり、数字は“予言”ではなく“行動設計”なのです。
4. 制度と感情の交差点にある“防災の再設計”
この発表は、科学の限界を認めながら、制度としてどう生活者に伝えるかという“誠実な揺らぎ”の表現です。
- 「60%に下がった」と捉えるのは誤解
- 「90%に上がった」と捉えるのも誤解
- 正しくは、「不確実性を含めても、依然として高い確率である」
- → “その時”は確実に近づいているという前提で、備えを進めるべき
5. タグ
#南海トラフ地震の制度設計#確率と不確実性の交差点#地震学の限界と生活者の備え#数字の意味と行動設計#防災と確率の再構築