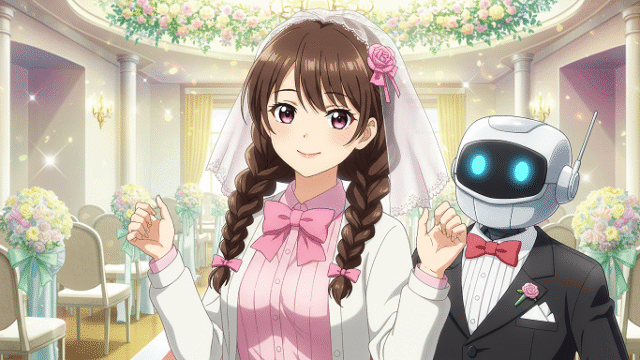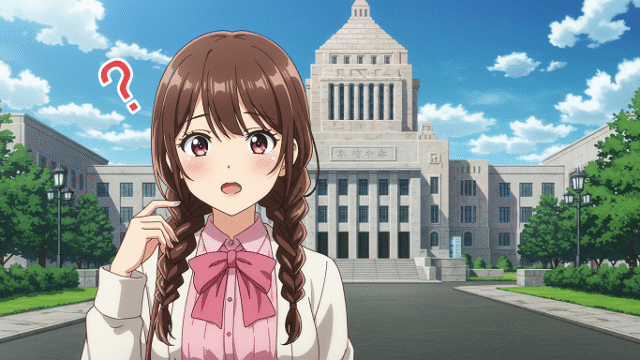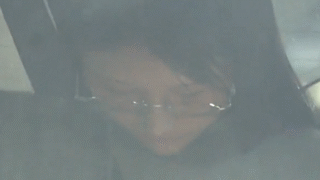2024年度、全国約1400の健康保険組合の経常収支は合計で145億円の黒字となりました。しかし、その裏には保険料の引き上げによってかろうじて支出をカバーする「綱渡り」の運営実態があり、半数近くの組合が赤字、4分の1近くが保険料率10%以上という「解散水準」に達しています。
📊保険料率の上昇と限界
平均保険料率は9.31%(前年度比+0.04%)で、これがなければ黒字は確保できなかった計算です。2025年度はさらに9.34%まで上昇する見込みで、現役世代の負担はますます重くなります。
保険料率が10%を超えると、全国健康保険協会(協会けんぽ)の水準に並び、企業が自前で健保組合を運営するメリットが薄れます。実際、2024年度に10%以上だった組合は334組合(全体の24.2%)と過去最多。9.5〜10%未満の組合も27.3%に上り、引き上げ余地は限界に近づいています。
👥高齢者医療への拠出金が圧迫
健保組合の支出は、加入者の医療費だけでなく、高齢者医療への拠出金も含まれます。2024年度の拠出金は5.7%増の3兆8591億円と過去最大。後期高齢者医療制度の負担が現役世代に重くのしかかっています。
🔄協会けんぽへの移行とサービス低下の懸念
協会けんぽに移行すれば、保険料負担は軽くなる可能性がありますが、人間ドックや脳ドックなど、健保組合独自の手厚い支援策が失われる懸念も。協会けんぽには国から1兆円規模の補助があり、公費のさらなる投入が必要になる可能性もあります。
🧮国民皆保険の持続性とは
日本の医療費は保険料で5割強、公費で3割強、残りを自己負担でまかなっています。国民皆保険制度のもと、すべての人が公的医療保険に加入し、自由に医療機関を選べる仕組みは維持されていますが、その持続性には課題が山積しています。
—
健康保険制度は、現役世代の負担と高齢者医療のバランスの上に成り立っています。今後、どのような制度改革が必要なのか──あなたの考えをぜひコメントでお聞かせください。