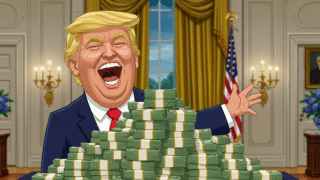2025年10月、東京都は全国で初めて「無痛分娩」の一部費用を助成する制度を開始します。少子化対策の一環として、出産時の痛みを軽減する選択肢を支援するこの取り組みは、多くの妊婦から歓迎されています。しかし、現場を見渡すと、制度の限界や課題も浮かび上がってきます。
🌸「幸せなお産」を求めて
2児の母・エリさん(仮名)は、2回とも無痛分娩を選択。「痛みはそれほどなく、幸せなお産だった」と語ります。硬膜外鎮痛法による麻酔で、陣痛の痛みを抑えながら、夫と談笑する余裕もあったそうです。
無痛分娩は、体力の消耗を抑え、産後の回復を早める効果があるとされ、高齢出産の増加に伴い希望者も増加傾向にあります。
💰費用というハードル
都の調査では、出産経験者の6割が無痛分娩を希望していたものの、半数近くが断念。その理由は「費用が高い」「施設が近くにない」など。実際、無痛分娩には5万~20万円の追加費用がかかり、エリさんの第1子出産費用は約100万円に達したといいます。
東京都の助成制度では、都内在住の妊婦が認定医療機関で無痛分娩を受けた場合、最大10万円が補助されます。
📈助成と値上げの「いたちごっこ」
助成制度の開始に合わせて、都内の一部クリニックでは無痛分娩の値上げを公表。出産育児一時金の増額に伴う費用上昇もあり、「いたちごっこ」との指摘も出ています。
医療経済学の田倉智之教授は、「物価高や人員確保など、値上げには理解すべき事情がある」としながらも、「政策の効果が薄れてしまう可能性があるため、検証が必要」と語ります。
🏥産科医療の厳しい現実
少子化による分娩数の減少で、2023年度には全国の分娩施設の42.4%が赤字経営。体制維持のための値上げは「やむを得ない」との声もあります。
政府は2026年度にも、標準的な出産費用の自己負担を無償化する制度を検討していますが、無痛分娩は対象外の見通し。厚労省幹部は「地域格差を広げる懸念がある」と語り、現時点では他の道府県に同様の助成制度は見られていません。
—
無痛分娩は、妊婦の選択肢を広げ、出産の不安を軽減する大切な手段です。助成制度が本来の目的を果たすためには、価格の透明性と制度の持続可能性が問われます。
あなたはどう思いますか?「痛み少なく、幸せなお産」を実現するために、どんな支援が必要だと感じますか。コメントでぜひご意見をお聞かせください。