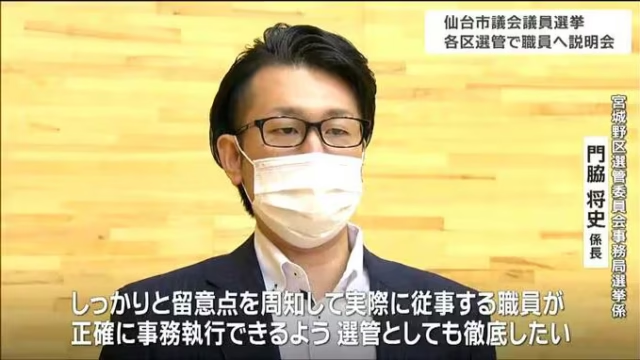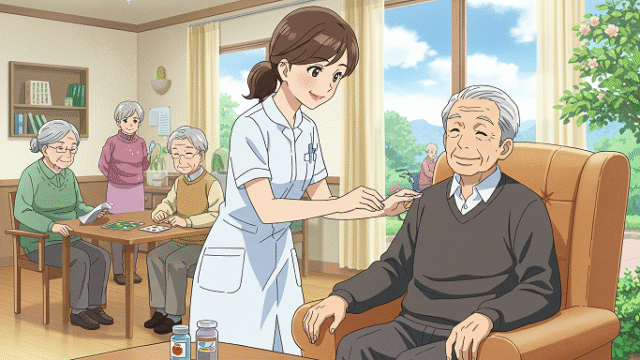今年の新米、店頭価格は5キロ5000円前後。 昨年の1.5倍以上という高騰ぶりに、生活者の「ちょっと高すぎでは?」という声が聞こえてきます。 でもその裏側では、生産者が「原価を知ってほしい」と訴えているのです。
🧭 価格高騰の背景:米不足と仕入れ競争の余波
- 昨年の米不足を受け、JAと民間業者が仕入れ競争
- 店頭価格は急騰、業務用は外国産米へ切り替えが進行
- JA全農ふくれんは「需要開拓の努力が必要」と危機感を表明
この構造は、「米が余るかもしれないのに、売れない」という制度的ジレンマ。 生活者の財布と制度の在庫が、すれ違い始めているのです。
🚜 生産者の声:「原価を知らずに価格だけ見ないでほしい」
福岡県筑紫野市の藤井徳浩さん(65)は、16ヘクタールの水田を管理する米農家。 彼が語るのは、“米の値段”ではなく“米の原価”。
- コンバイン1台:約2000万円
- 燃料・資材:年々高騰
- 機械類の更新:不可避な大規模投資
「原価が公表されないまま、価格だけが注目されている」 「ようやく米の価格が戻ってきた。その中でコストも増えている」
この言葉は、「食べる側と作る側の距離」が広がっていることへの静かな警鐘です。
🍚米は“価格”ではなく“関係性”で選ぶ時代へ
この新米騒動は、単なる価格問題ではありません。 それは、生活者が“食の背景”をどれだけ知っているかという問いでもあります。
- 米の価格は、制度・資材・気候・流通の複合構造で決まる
- 生産者は、「買ってほしい」ではなく「知ってほしい」と訴えている
- 生活者は、「高いか安いか」ではなく「なぜその値段なのか」を問うべき時代へ
🗂️ タグ
#新米価格の構造分析#食べる側と作る側の距離#農業制度と生活者の接点#米の原価と価値の再設計#食の背景を知る暮らし