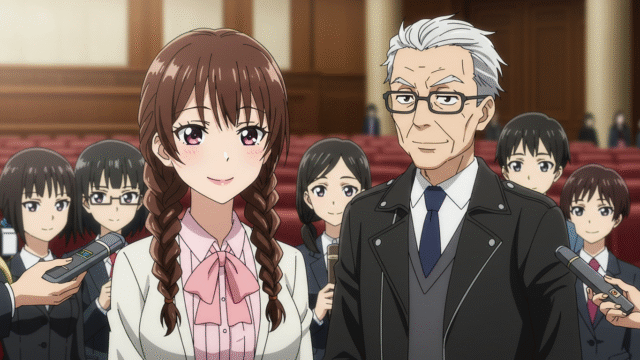5年に一度の国勢調査が始まりました。 政策立案の基礎資料となる、最も重要な国の統計調査──その裏側で、調査員たちは今日も玄関先に立っています。
🧭 調査員という“国家の足元”
調査員は、総務相が任命する非常勤の国家公務員。 報酬は数万円。 でも、その仕事は「紙を配る」だけではありません。
- 1人あたり50〜130世帯を担当
- 空き家・留守宅には最低3回訪問
- 調査員証と専用袋を身につけて訪問
- 夜は怪しまれ、朝は怒られる
京都市の調査員(81歳)は語ります。 「前回はコロナ禍でポスト投函だったが、今回は対面。かなり大変だ」 この言葉に、制度の重みと生活者の距離感が詰まっています。
📉 なり手不足という“制度の綻び”
- 自治会の加入率低下
- 詐欺被害の増加による防犯意識の高まり
- 定年延長で“担い手世代”が減少
宇治市では600人の目標に対し、確保できたのは550人。 京都府は今回初めて調査員を公募し、170人が応募。 これは「制度が生活者の信頼を前提にしていた構造」が、静かに崩れ始めていることを示しています。
🧑💻 回答はネットでも可能──でも“紙の現場”は残る
調査書類は戸別配布が原則。 回答はインターネットでも可能。 京都府は植物園やイオンモールでネット回答体験イベントも開催予定。
でも、調査員は今日も歩いています。 ポストに手を伸ばし、インターホンを押し、 「怪しまれないように」「怒られないように」 国家の統計は、生活者の足音で支えられているのです。
🗂️ タグ
#国勢調査の現場から#制度と生活者の距離感#調査員という国家の足元#なり手不足と制度設計