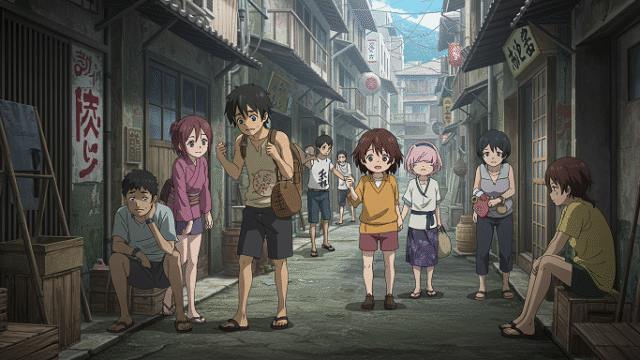「再実験をしたいなら、土下座して頼め」──これは、2025年6月、愛知県の豊田工業高等専門学校で実際に教員が生徒に向けて発した言葉です。 そして、生徒はその言葉に従い、実際に土下座をしました。
この一件は、単なる“不適切な指導”ではありません。 それは、教育という名のもとに、制度外の力が個人の尊厳を踏みにじった瞬間です。
「百聞は一見にしかず」ではなく「百見しても言えない」
実習で失敗した生徒が、再実験を申し出た。 そのとき、教員は「土下座して頼め」と言った。 冗談ではなかった。 生徒は、周囲の視線を感じながら、膝をつき、頭を下げた。
この場面を想像してほしい。 実験室の床に頭をつける若者と、それを見下ろす教員。 その空気を、誰が止められただろうか。 誰が「それはおかしい」と言えただろうか。
教育現場に潜む“制度外の支配”
学校側は「きわめて不適切な指導」として謝罪し、再発防止を約束した。 でも、問題は「なぜそれが起きたか」ではなく、「なぜそれが許容される空気があったか」だ。
- 教員の発言は、指導ではなく屈辱の強要
- 生徒は、評価と進級のために沈黙を選ばざるを得なかった
- 学校は、「厳正に対処する」とコメントしたが、制度の中で何が起きていたかは語られていない
これは、「教育の名を借りた支配」が、制度の隙間で正当化されてしまう危うさを示している。
「指導」と「屈辱」の境界線はどこにあるのか
教育とは、知識を伝えるだけでなく、人間としての尊厳を守る場であるべきだ。 その尊厳を奪うような言葉や態度が、“指導”という名で許されるなら、 それは教育ではなく、制度外の支配だ。
この事件は、教育現場における「指導」と「屈辱」の境界線を問い直す契機だ。 そして、私たち生活者が「それはおかしい」と言える社会であるかどうかを、静かに試している。
タグ
#教育現場の権力構造#制度外のハラスメント#生徒の沈黙と選択#指導と屈辱の境界線