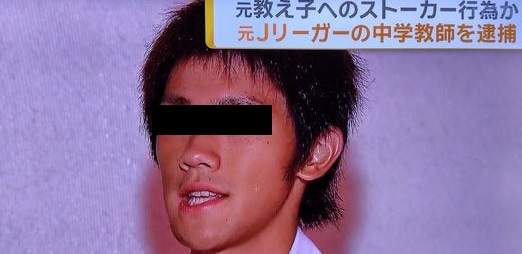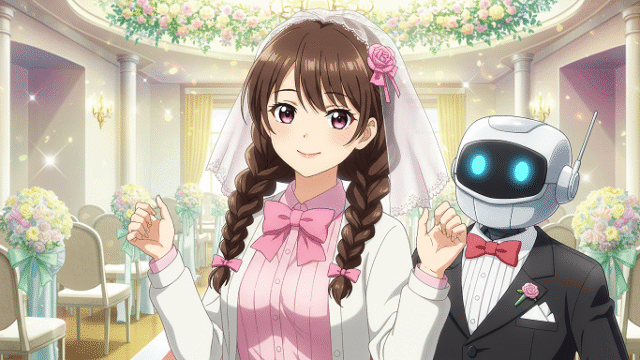「北九州市がムスリム対応の給食を決定した」──そんな情報がSNSで拡散され、わずか数日で抗議の電話・メールが1000件以上に達しました。 でも、これは事実ではありません。 そして、誤情報がもたらしたのは、制度の誤解と生活者の感情の暴走でした。
🧭 何が起きたのか:事実と誤解の構造
- 2023年6月:ムスリムの女性が「宗教上の禁忌に配慮した給食を」と陳情
- 2023年8月:市議会で継続審議に→2025年2月に廃案
- 同月:市が「にこにこ給食」を実施(アレルギー対応で豚肉除去) → 結果的にムスリムにも対応可能だったが、制度としての導入ではない
この流れが「ムスリム給食が制度化された」と曲解されて拡散。 SNSでは「外国人優遇」「移民政策」といった排外的なメッセージと共に広まりました。
📉 誤情報がもたらした“制度の混乱”
- 市教委には抗議が殺到し、業務に支障
- インド・テランガナ州との友好協定まで「移民受け入れ策」と混同される
- 市は「事実はない」と公式に否定する事態に
これは「制度の説明不足」ではなく、情報の流通構造そのものが生活者の感情を煽った例。 “食”という身近な制度が、感情のトリガーになった瞬間です。
🍱 食と共生は“制度”ではなく“関係性”で築くもの
この件は、単なる誤情報の拡散ではありません。 それは、生活者が制度をどう受け止めるか、そして制度が生活者にどう届くかのすれ違いです。
- 給食は「制度」ではなく「関係性」──誰が、どんな背景で、何を食べるか
- 共生は「配慮」ではなく「理解」──その人の事情を知ることから始まる
- 情報は「正しさ」ではなく「伝わり方」──制度の意図がどう曲解されるかを設計する必要がある
🗂️ タグ
#給食制度と共生の構造#誤情報と制度のすれ違い#生活者の感情と情報設計#食と宗教の接点#SNSと制度の交差点