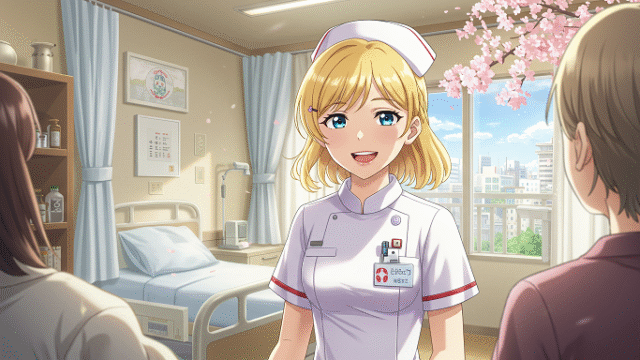2025年秋、新米の流通が始まったにもかかわらず、コメ価格が再4000円を突破。 政府の備蓄米放出による価格抑制効果は、わずか3か月で息切れ。 「高くて手が出ない」「生活するにはつらい」といった声が、スーパーの売り場から聞こえてきます。

📊 価格高騰の背景
- 新米流通=価格下落のはずが、逆に高騰
- JAによる集荷競争の過熱で、農家への仮払い「概算金」が過去最高水準に
- 例:新潟県産コシヒカリ(玄米60kg)概算金=3万円(前年比+76%)
農水省の調査でも、概算金は昨年比で3〜7割高。 卸業者は「価格よりも確保が優先」と語り、“バブル状態”との声も。
🏦 備蓄米効果は一時的
- 7月:備蓄米放出で平均価格は3500円台に下落
- 9月:新米流通で再び4000円超え
- スーパーでは「価格転嫁すれば客足が遠のく」として、2割程度の値上げに抑制
🌾 需給見通しと不透明感
農水省は2025年産の主食用米について…
- 生産量が需要量を17万〜48万トン上回る見通し
- 民間在庫量は2026年6月末時点で最大229万トン(過去最多水準)
しかし、猛暑による収穫量減少の懸念もあり、 茨城大・西川教授は「米価が下落に向かうタイミングは予測困難」と指摘。
🧭価格だけでなく“構造”を問うべき時
コメは生活者にとっての必需品であり、文化の根幹。 価格高騰は単なる物価問題ではなく、農業構造・流通制度・備蓄政策の限界を映し出しています。 「備蓄米=価格安定」の構図が崩れた今、“誰のための制度か”を問い直すタイミングかもしれません。