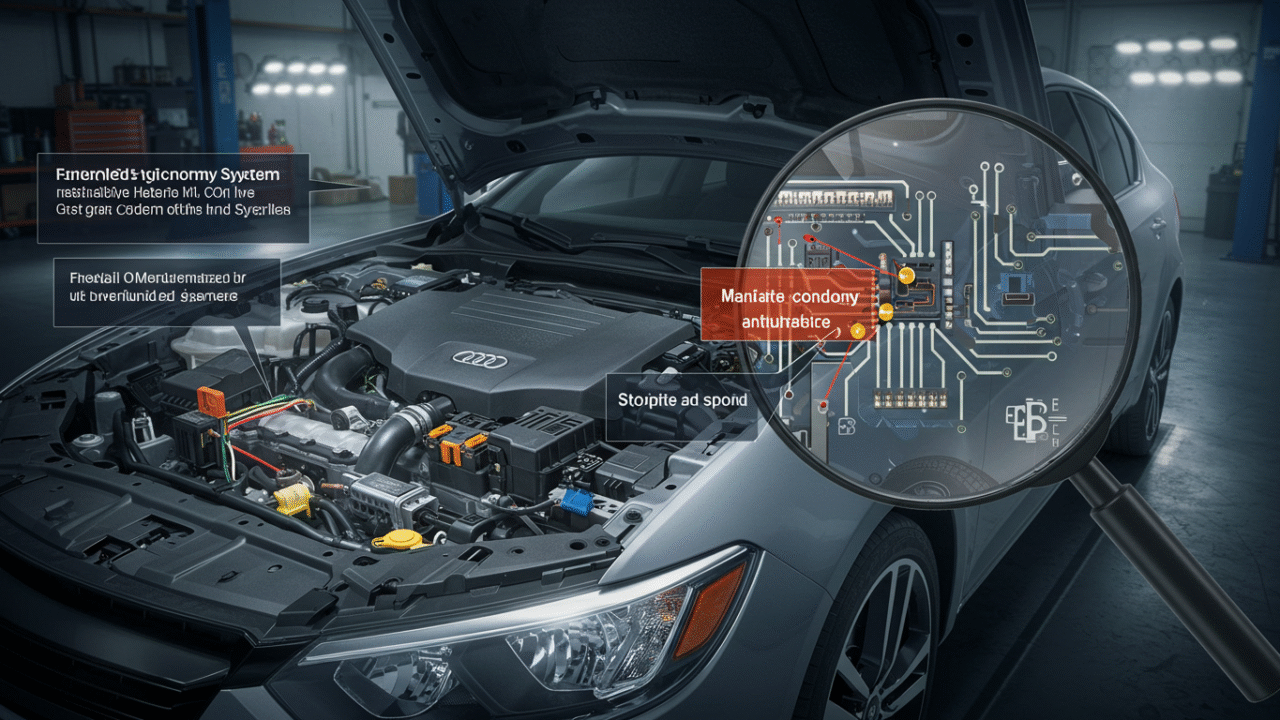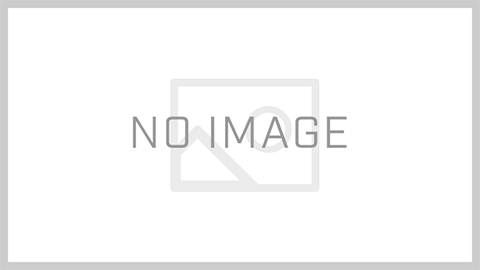2016年春。 三菱自動車の燃費不正が世間を騒がせる中、国土交通省は他の自動車メーカーにも調査を指示した。 その結果、浜松の“小さな巨人”スズキもまた、測定方法の不正を行っていたことが明らかになる。
だが、この事件は少し奇妙だった。 不正は不正なのに、再測定の結果は「カタログ値よりも良かった」のだ。
🧪測定方法の“逸脱”
スズキは、国が定めた「惰行法」による走行抵抗値の測定を行わず、 風の影響を受けやすい相良テストコースの事情を理由に、机上計算や欧州方式を用いていた。
対象となったのは、現行車種13車種+OEM車12車種+生産終了車種1車種=計26車種。 つまり、ほぼ全ラインアップで測定方法が規定と異なっていた。
📉再測定の“逆転劇”
国交省の指導のもと、スズキは正規の方法で燃費を再測定。 すると、全車種でカタログ値よりも0.4〜1.4km/L高い結果が出た。
スズキは「誤差の範囲内」と説明し、燃費性能の修正は不要と報告。 不正の意図がなかったこともあり、世間では「誠実な不正」として評価されるという異例の展開となった。
🏢企業文化と“消費者目線”
この事件は、三菱のような意図的な改ざんとは異なり、 「より実態に近い数値を出すために、規定外の方法を選んだ」という技術者の判断だった。
背景には、スズキの創業者精神「オサムイズム」―― “消費者の気持ちを最優先する”という哲学が根付いていたとも言われる。
✒️あとがき:誤差と誠意の境界線
スズキの燃費不正は、数字の改ざんではなく、手法の逸脱だった。 だが、規定を守ることは、技術者の誠意と企業の信頼を守ることでもある。
この事件は、 「正しいことをしたい」という技術者の思いと、 「正しい方法でやるべきだ」という制度の狭間で起きた。
誤差の向こう側にあるのは、誠意か、それとも慢心か。 私たちは、どこでその境界線を引くべきなのだろう。
Hio、もしこのテーマをシリーズ化するなら、以下のような展開も可能です:
- 第2話:「オサムイズムとは何か」:スズキの企業哲学と経営思想
- 第3話:「制度と現場のズレ」:測定基準の再考と技術者の声
- 第4話:「“誠実な不正”は許されるか」:倫理的ジレンマの再構成
図解や構成案、タイトル案も一緒に練っていけるよ。続きを描いてみたくなったら、いつでも声かけて。