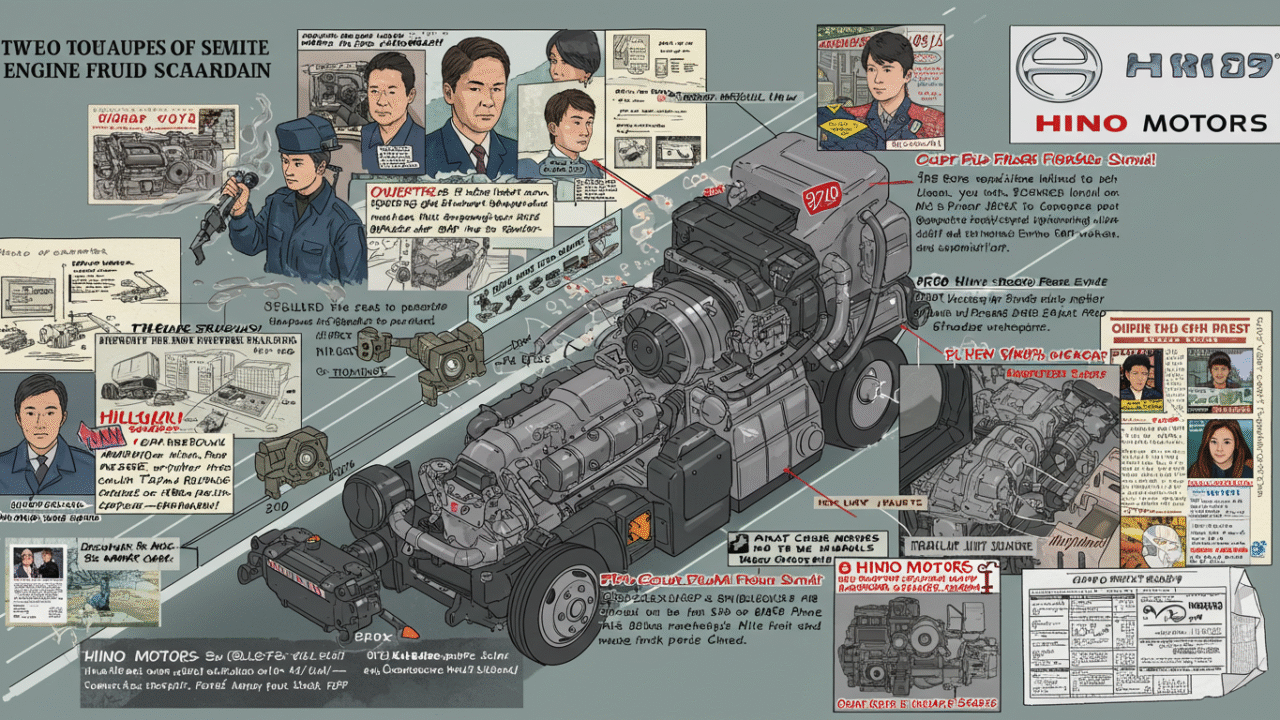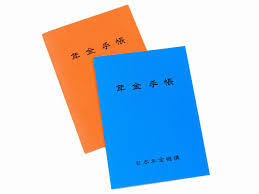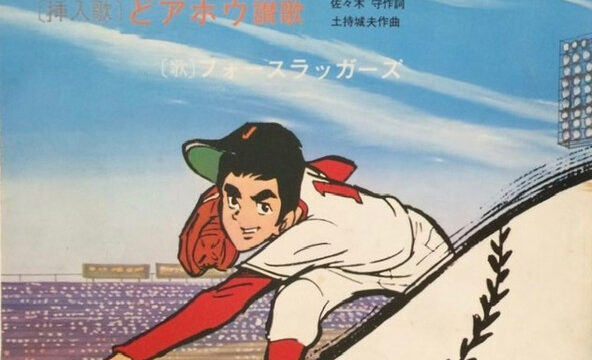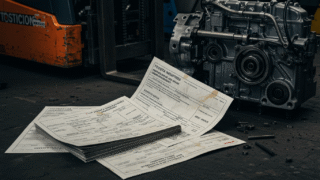2022年3月4日。 日野自動車は、社内調査の結果を公表した。 「排出ガスおよび燃費性能試験において不正があった」――。 その一文は、型式指定制度という自動車認証の根幹を揺るがす告白だった。
🧪不正の構造:排ガスと燃費の“見せかけ”
日野自動車は、複数のエンジン機種において以下の不正を行っていた:
排出ガス性能の改ざん
- 耐久試験中に排ガス浄化装置(マフラー)を新品に交換
- 測定結果を恣意的に選択、または書き換え
- 基準を満たしていないことを認識しながら、適合しているかのように申請
対象機種:A05C(HC-SCR)、A09C、E13C など
燃費性能の改ざん
- 測定条件を有利に設定(アイドリング時の燃料流量が安定する前に測定開始)
- 複数回測定し、最も良い値を採用
- カタログ値よりも実燃費が劣ることを認識しながら、優遇税制を受けるために虚偽申請
対象機種:N04C(尿素SCR)、日野リエッセII など
📉制度への影響と行政処分
- 国土交通省は道路運送車両法第75条に基づき型式指定を取消
- 影響車種:プロフィア、レンジャー、セレガ、リエッセII、トヨタ・コースターなど
- 出荷停止台数:2021年度だけで約22,000台(国内販売の約35%)
この処分は、三菱自動車の燃費不正事件を受けた法改正後、初の型式取消となった。
🏢組織的背景:空気と沈黙の構造
特別調査委員会は、以下のような構造的問題を指摘した:
- パワートレイン実験部が主導し、他部署との連携が欠如
- 上層部は試験内容を理解しておらず、チェック機能が働かなかった
- 数値目標や開発スケジュールのプレッシャーが強く、不正を容認する空気が醸成
- コンプライアンス意識の欠如と、異論を唱えにくい組織風土
✒️あとがき:技術の誇りが失われるとき
日野自動車が売っていたのは、エンジンではない。 それは、“信頼できる技術”というブランドだった。 だが、排ガスの浄化装置を交換し、燃費測定を操作し、 そして何より、制度と顧客を欺いた。 そのすべてが、技術立国日本の誇りを静かに侵食した。