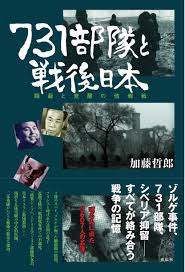2015年7月21日、東京・芝浦。 東芝本社で開かれた記者会見。 田中久雄社長は、10秒以上頭を下げた後、静かに口を開いた。
「経営責任を明らかにするため、本日をもって辞任します」――。
その瞬間、日本を代表する総合電機メーカーの信頼は、音を立てて崩れ落ちた。
🧩事件の概要
- 期間:2008年度〜2014年度第3四半期
- 不正額:累計約1,562億円の利益水増し
- 発端:証券取引等監視委員会への内部通報(2015年2月)
- 手法:工事進行基準の操作、経費の先送り、在庫評価の改ざんなど
- 影響:歴代3社長が辞任、株価急落、課徴金約73億円
🧪「チャレンジ」と呼ばれた圧力
東芝では、社長が各事業部に対して「チャレンジ」と呼ばれる収益目標を設定していた。 達成できなければ事業撤退も示唆される――そんなプレッシャーの中、現場は数字を“作る”しかなかった。
- 工事原価を過小に見積もり、利益を前倒し計上
- 映像事業では広告費や物流費を翌期に“キャリーオーバー”
- パソコン部品の“押し込み販売”で売上を水増し
それは、経営陣の指示がなくとも、空気が命じていた不正だった。
🕵️♂️第三者委員会の調査
2015年5月、東芝は元検事長・公認会計士らによる第三者委員会を設置。 調査は2ヶ月に及び、7月に報告書が公表された。
結論はこうだった:
「経営トップを含めた組織的な関与があった」
しかし、社長らは「直接的な指示はしていない」と関与を否定。 監査法人(新日本有限責任監査法人)も見抜けなかった責任を問われ、金融庁から業務改善命令を受けることになる。
📉崩れた信頼と再建への道
- 有価証券報告書の提出が2ヶ月以上遅延
- 2015年3月期は378億円の赤字に転落
- 株価は報告書公表後に369円まで下落
- 社外取締役の導入、内部統制の強化へ
だが、失われた信頼は、数字では回復できない。
✒️あとがき:チャレンジの意味を問い直す
「チャレンジ」という言葉は、本来、前向きな挑戦を意味する。 だが、東芝ではそれが“数字の強要”となり、現場を追い詰め、不正を生んだ。
この事件は、企業文化がいかに会計倫理を歪めるかを示した。 そして、監査制度の限界、内部通報の重要性、経営陣の責任のあり方―― 私たちは、何をもって「健全な企業」と呼ぶのかを、改めて考えなければならない。