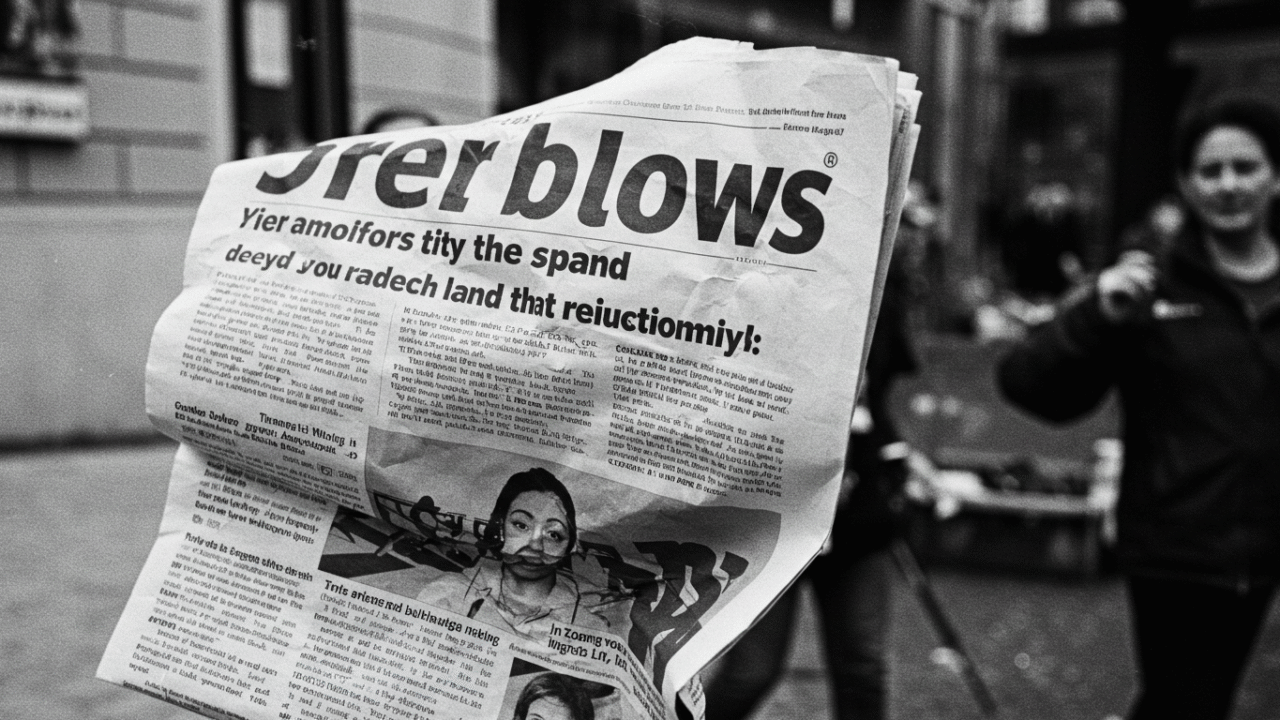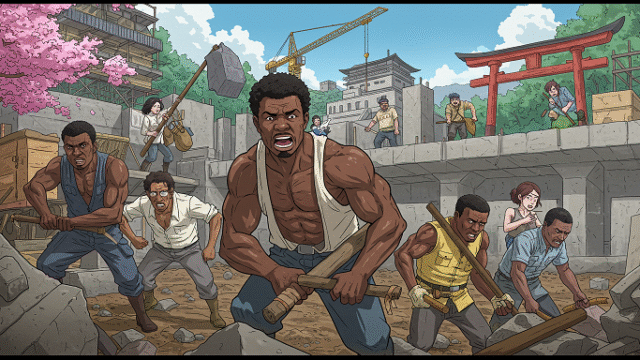GHQ・政界・財界が交錯した“昭電疑獄”の全貌
🕰️1948年、東京。焼け跡の街に、復興の光と影が交錯していた。
戦後の混乱期、日本は「復興」という名の希望を掲げながら、政治・経済・官僚・GHQが複雑に絡み合う時代を迎えていました。その中で起きたのが、昭和電工事件──戦後最大級の汚職事件です。
この記事では、事件の流れを物語形式で追いながら、若い読者にもわかりやすく「何が問題だったのか?」を解きほぐしていきます。
🏭第1章:昭和電工と“国家の使命”
昭和電工の社長・日野原節三は、肥料工場の拡張という国家的プロジェクトを進めるため、復興金融金庫から23億円の融資を引き出します。
しかしその裏で、政官界に“運動費”と称した巨額の資金が流れていたのです。
「これは国家のためだ。多少の金が動いたとしても、それが何だというんだ──」
この言葉が、事件の核心を物語っています。
🕵️♂️第2章:警視庁とGHQ──正義は誰のもの?
捜査を指揮したのは、警視庁捜査二課長・秦野章。彼は政界の大物たちの名前が浮かび上がる中、GHQの干渉にも屈せず捜査を続けました。
そして、ある外国人記者に極秘資料を託します──
「GHQは、日本の警察の邪魔をするのか?」
この一言が、戦後日本の主権と正義を問い直すきっかけとなりました。
🏛️第3章:政界崩壊──芦田内閣の終焉
福田赳夫、大野伴睦、西尾末広──次々と逮捕される政界の要人たち。そしてついに芦田均首相までもが拘置所へ。
「私は何も知らなかった。だが、責任は取らねばならない」
この事件は、戦後初の“内閣崩壊”を引き起こしました。
⚖️第4章:裁かれたのは誰か?
裁判の結果、有罪となったのは日野原社長と栗栖赳夫のみ。他の政治家は無罪となり、GHQ関係者への追及は一切行われませんでした。
「影も形もないものを一生懸命にすくい上げようとしている──それが検察の姿だった」
この言葉が、事件の“限界”を象徴しています。
🧠まとめ:昭和電工事件が私たちに残した問い
この事件は、戦後日本の民主化の限界、外圧と内圧のせめぎ合い、そして「正義とは何か?」という根源的な問いを私たちに突きつけました。