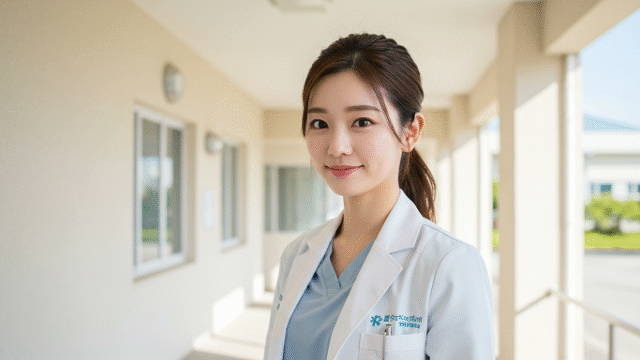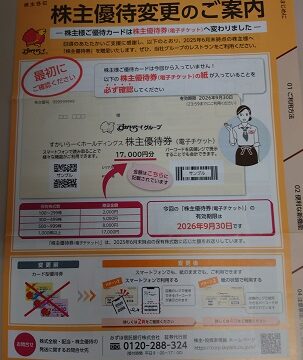🌙プロローグ:静かな夜に、牛乳が毒に変わる
2000年6月25日、和歌山。 子どもたちが飲んだ「雪印低脂肪乳」で、嘔吐と下痢の症状が出始めた。 最初は“夏風邪”と疑われたが、症状は次々と近畿一円に広がっていく。
その数、14,780人──戦後最大の集団食中毒事件となった。
⚙️第1章:停電と沈黙
事件の発端は、北海道・大樹工場での3時間の停電。 タンクに残された脱脂乳は、摂氏20度以上で約4時間放置され、 黄色ブドウ球菌が増殖。毒素「エンテロトキシンA」が発生した。
本来なら廃棄すべき原料だった。 だが、工場は「殺菌すれば安全」と判断し、製品化してしまう。
その後、異常を把握した製造課長は、叱責を恐れて隠蔽した。
🏭第2章:大阪工場へ──毒素は流通する
汚染された脱脂粉乳は大阪工場へ送られ、 「低脂肪乳」や「のむヨーグルト」などに加工されて出荷された。
6月21日から29日までの間に製造された製品は、 スーパーを通じて近畿地方一円に広がっていった。
📢第3章:企業の沈黙と行政の焦り
6月27日、大阪市保健所が食中毒の疑いを通報。 だが、雪印は株主総会のため対応を先延ばし。 社告も出さず、回収も遅れた。
ついに大阪市が独自に記者発表を行い、 雪印は深夜になってようやく製造休止を発表。
社長・石川哲郎は会見で「君、それは本当かね」と驚きの声を漏らす。 企業の情報共有は、完全に崩壊していた。
🧠エピローグ:信頼の崩壊と倫理の問い
この事件は、単なる衛生管理の失敗ではない。 それは、“企業の沈黙”が人々の健康を脅かした瞬間だった。
- なぜ現場の声が黙殺されたのか?
- なぜ「殺菌すれば安全」という論理が優先されたのか?
- なぜ社内で真実が共有されなかったのか?
雪印はその後、グループ解体へと進み、 「雪印メグミルク」として再出発することになる。
だが、“寝てないんだよ!”という社長の言葉は、 企業の危機対応の象徴として、今も語り継がれている。