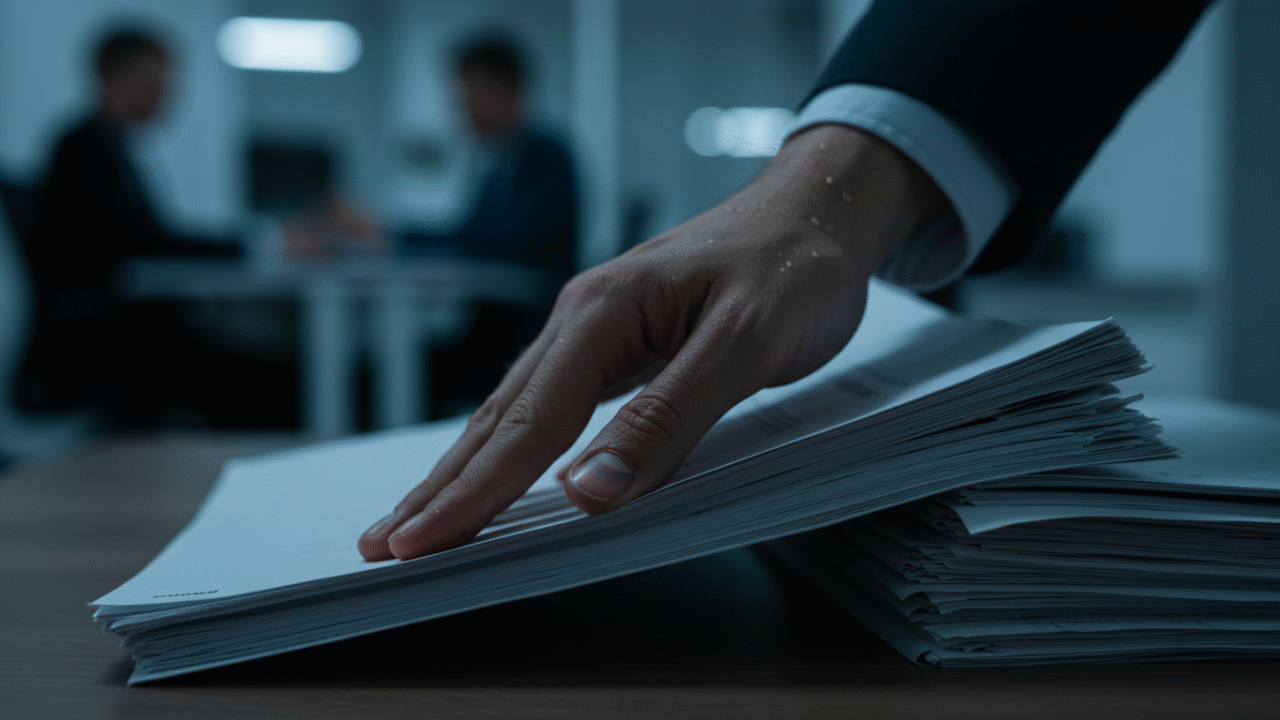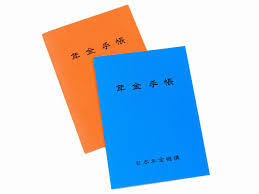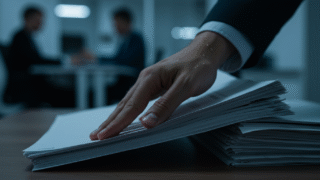🕰️プロローグ:匿名の告発
2000年6月、運輸省に1通の通報が届いた。 差出人は三菱自動車の社員。 内容は驚くほど具体的だった。
「品質保証部の更衣室の空きロッカーを調べよ」 「岡崎工場と本社のデータを突き合わせよ」 「“Hマーク”のクレーム情報が隠されている」
それは、23年間にわたる“隠蔽の設計図”だった。
🧑💼第1章:PマークとHマーク──二重管理の闇
三菱自動車は、顧客からの不具合情報を10段階で管理していた。
- Pマーク:運輸省に報告する“表向き”の情報
- Hマーク:社内で隠す“秘匿”情報
1977年からこの仕組みは続いていた。 1992年には東芝製の品質管理システムでデジタル化され、 “隠すための仕組み”が完成した。
🔧第2章:ヤミ改修という慣習
三菱は、リコールを避けるために「ヤミ改修」を行っていた。 顧客にこっそり連絡し、修理する。 運輸省には報告しない。
対象車種は69万台以上。
- ランサー
- ギャラン
- パジェロ
- シャリオグランディス
- 大型トラック・バス
不具合は、エンジン停止、燃料漏れ、スライドドアの故障など多岐にわたった。
⚠️第3章:事故と死
2002年1月、横浜市瀬谷区。 三菱製の大型トレーラーのタイヤが走行中に脱落。 歩道を歩いていた母子を直撃。 母親は死亡、幼児2人が負傷。
原因は、ハブ(車輪を支える部品)の破損。 三菱は「整備不良」と主張したが、 実際には1992年以降、同様の事故が57件も起きていた。
⚖️第4章:逮捕と裁判
2004年、三菱ふそうの元会長・元常務ら7人が逮捕。 道路運送車両法違反(虚偽報告)、業務上過失致死傷などの容疑。 法人としての三菱自動車も刑事告発された。
罰金はわずか数十万円。 だが、企業の信頼は地に落ちた。
📉第5章:崩壊と再建
- ダイムラー・クライスラーは資本提携を打ち切り
- CEOは辞任
- 販売台数は激減
- 社員の大量退職
三菱グループ(三菱重工・商事・UFJ銀行)が救済に乗り出し、 倒産は免れた。 だが、ブランドは“走る棺桶”と揶揄された。
🧠エピローグ:隠す文化の終わり
この事件は、企業が「不具合を隠すこと」を“文化”としていたことを暴いた。 内部告発がなければ、事故は繰り返されていたかもしれない。
- なぜリコールを避けたのか?
- なぜ命より利益を優先したのか?
- なぜ罰則は軽かったのか?
今も、問いは残っている。