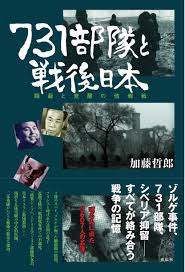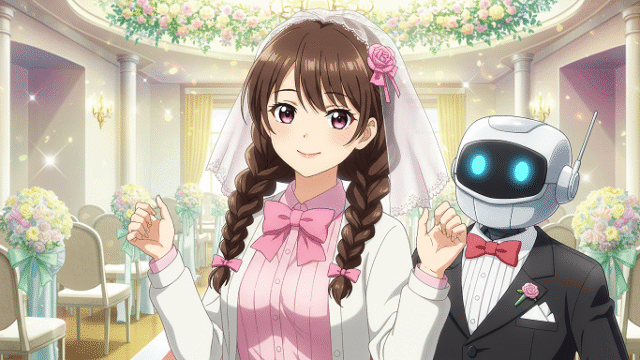🧾事件の背景──税率をめぐる静かな攻防
1965年、政府が液化天然ガス(LNG)への新規課税を提案。 この税率が高すぎると困るのが、LNGを燃料に使う業界──大阪のタクシー業界もそのひとつでした。
大阪タクシー協会は、衆議院運輸委員の寿原正一・関谷勝利に献金を渡し、法案の修正を働きかけたとされます。 結果、税率は大幅に引き下げられました。
でも、ここで疑問が浮かびます。 法案を修正したのは運輸委員ではなく、大蔵委員会。 では、運輸委員が“他の委員に働きかける”ことは、職務権限なのか?
この問いが、事件の核心でした。
⚖️裁判と“職務権限”の解釈
1967年、協会会長と理事が贈賄容疑で逮捕。 同年12月、寿原・関谷も受託収賄容疑で逮捕。 その後、寿原は一審中に死去、関谷は上告中に死去。 協会会長も上告中に死去。 唯一、協会理事のみ1988年に有罪が確定しました。
裁判では、「他の委員に働きかける行為も職務権限に含まれる」と解釈され、有罪判決が出ました。 この解釈は、政治家の“影響力”がどこまで法的責任を伴うかを問う、重要な前例となりました。
🧠この事件が突きつけるもの
この事件が私たちに突きつけるのは、次のような問いです:
- 業界団体が政治家に働きかけることは、どこまで許されるのか?
- “職務権限”とは何か?影響力の行使は、どこまでが職務なのか?
- 法案の修正は、誰の手によって、どんな力学で行われているのか?
そして何より── 「税率は誰が決めているのか?」という根本的な問い。
📝まとめ:昭和の事件に、令和の私たちが学ぶべきこと
大阪タクシー汚職事件は、昭和の政治と業界癒着の象徴でありながら、今の政治にも通じる構造的な問題を孕んでいます。 ロビイングと汚職の境界線。 政治家の職務と影響力の定義。 そして、制度の裏側にある“見えない力”。