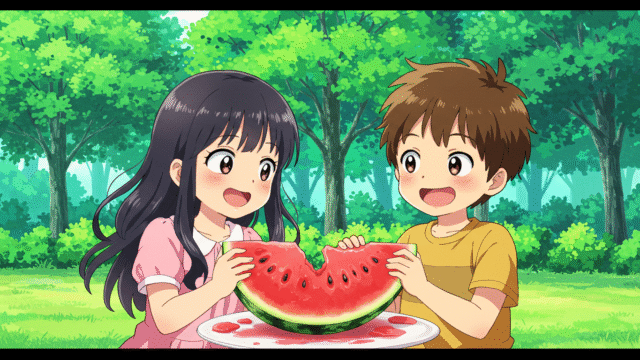鉄道と政治が交差した昭和初期の汚職スキャンダル
🔍事件の発端:浅草をめぐる鉄道戦争
1920年代後半、東京の鉄道網は急速に拡張していました。そんな中、京成電気軌道(現在の京成電鉄)は浅草への乗り入れを目指していましたが、ライバルの東武鉄道に先を越されてしまいます。
- 京成は1923年から6度にわたり浅草乗り入れを申請
- 6度目の申請時、政界への賄賂が発覚
- 工作費は16万円(現在の価値で約3000万円以上)
🧑⚖️政界・メディアを巻き込んだ汚職劇
この事件は単なる鉄道会社の焦りでは終わりませんでした。東京市会議員の半数が関与し、衆議院議員や新聞社の幹部までが逮捕される事態に。
- 京成社長・本多貞次郎が逮捕
- 衆議院議員:三木武吉・中島守利(贈賄幇助)、小俣政一(収賄)
- メディア関係者:正力松太郎(読売新聞)、千葉博巳(東京毎日新聞)
🛤️その後の京成:浅草を諦めて上野へ
事件後も京成は浅草乗り入れを諦めず、工事延期を繰り返しましたが、1943年に正式に計画を断念。その代わり、筑波高速度電気鉄道を吸収し、日暮里経由で上野公園(現・京成上野)への乗り入れを実現しました。
- 1931年:浅草乗り入れ許可 → 東武が先に開通
- 1933年:京成上野駅開業
- 1943年:浅草乗り入れ計画を正式に中止
🚇30年越しの夢:浅草へつながった日
事件から約30年後の1960年、都営地下鉄1号線(現・浅草線)が開業。京成はこの路線への直通運転を開始し、ついに浅草乗り入れを果たしました。
- 都営浅草線開業:1960年
- 京成の悲願が地下鉄経由で実現
🧠この事件から学べること
京成電車疑獄事件は、鉄道インフラと政治・メディアの癒着がもたらすリスクを浮き彫りにしました。都市開発の裏側には、利権と競争が複雑に絡み合っていることを教えてくれます。
若い世代にとっても、「公共交通は誰のためにあるのか?」という問いを考えるきっかけになるはずです。