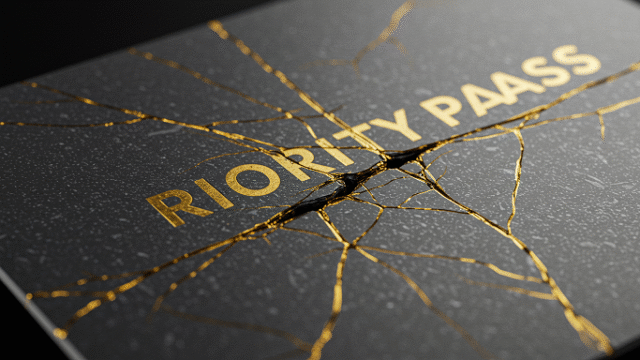🕰️前回までのあらすじ
イトマンは、絵画や不動産を使って巨額の資金を裏社会へ流していた。 その背後には、住友銀行から送り込まれた社長・河村良彦の存在があった。 だが、銀行はなぜこの異常な取引を止めなかったのか? 今回は、銀行の“沈黙”の理由を探る。
🧑💼登場人物
| 名前 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 河村良彦 | イトマン社長 | 住銀出身、銀行の意向を忠実に実行 |
| 住銀本店審査部 | 融資のチェック役 | 本来は“ブレーキ”をかける立場 |
| 住銀幹部 | 上層部 | イトマンを“痰壺”として利用 |
| 許永中 | 実業家 | 銀行の“盲点”を突く資金操作人 |
🧩第1章:痰壺の論理
住友銀行は、表向きは「堅実な銀行」だった。 だが、バブル期には“表に出せない融資”が増えていた。 そこで使われたのが――イトマン。
「銀行が直接やると問題になる。だからイトマンを使う」 河村は、住銀の“影の意志”を忠実に実行した。 イトマンは、銀行の“痰壺”として、地上げ・絵画・風俗などの資金を処理していた。
📉第2章:審査部の沈黙
本来なら、銀行の審査部が融資を止めるはずだった。 だが、イトマンへの融資は“特別枠”として扱われた。
- インペリアルウィングGC:640億円
- 銀座地上げ:664億円
- 絵画取引:680億円
審査部は、異常な価格や担保不足を知っていた。 それでも止めなかった。 なぜか? 「河村案件だから」――それがすべてだった。
🧠第3章:銀行の論理 vs 社会の倫理
銀行はこう考えていた。
- 損失が出ても、イトマンがかぶる
- 表に出なければ、住銀の信用は守られる
- 河村は“使い捨て”の駒
だが、社会はこう問う。
- なぜ銀行は責任を取らないのか?
- なぜ“痰壺”を作ったのか?
- なぜ内部告発はなかったのか?
銀行の論理は、社会の倫理とすれ違っていた。
⚖️第4章:裁判で語られなかったこと
裁判では、河村の責任が問われた。 だが、住銀本体の責任は曖昧なままだった。
- 幹部は証言を拒否
- 審査部は「記憶にない」と繰り返す
- 銀行は「イトマンの問題」として処理
結局、銀行は“沈黙”を貫いた。 そして、痰壺は捨てられた。
🧠エピローグ:沈黙は誰のために?
この物語は、企業と銀行の“使い捨て構造”を描いている。 誰かが責任をかぶり、誰かが沈黙する。 その構造は、今も変わっていないかもしれない。
✏️次回予告:
『許永中という男──逃亡と再逮捕のドラマ』 韓国に逃げた“黒幕”許永中。彼はなぜ逃げ、なぜ戻ったのか? その人生から、バブルの“裏の顔”を読み解きます。