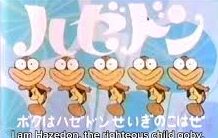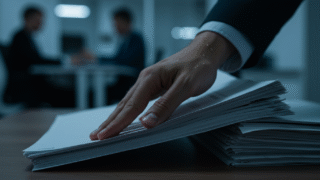🕰️プロローグ:静かな県境にて
1999年、青森県田子町と岩手県二戸市の県境。 緩やかな台地、牧草地、そして馬淵川水系の源流域。 その静かな原野に、異変が起きていた。
地元住民が見たのは、夜中に走る大型トラック。 積まれていたのは――首都圏から運ばれた産業廃棄物だった。
🧑💼第1章:共謀の構図
| 企業名 | 役割 | 拠点 |
|---|---|---|
| 三栄化学工業 | 投棄現場の管理 | 青森県八戸市 |
| 縣南衛生 | 廃棄物の委託元 | 埼玉県栗橋町(現:久喜市) |
縣南衛生は、首都圏の企業から廃棄物処理を請け負い、 三栄化学工業に“堆肥化”名目で委託。 だが、実態は――原野への不法投棄だった。
投棄された量は、推定125万トン。 国内最大級の産廃不法投棄事件となった。
🧪第2章:汚染の実態
- 投棄面積:約27ヘクタール(青森11ha+岩手16ha)
- 廃棄物の種類:焼却灰、汚泥、廃油、RDF(固形燃料)など
- 地下水汚染:VOC(揮発性有機化合物)による汚染が確認
- 原状回復費:約480億円
この地は、農業・畜産・水産業が盛んな地域だった。 だが、廃棄物はその土壌と水を静かに蝕んでいた。
⚖️第3章:捜査と裁判
1999年11月、岩手・青森県警が合同で強制捜査。 2000年、両社の幹部が廃棄物処理法違反で逮捕・起訴。
| 被告 | 判決 |
|---|---|
| 縣南衛生社長 | 懲役2年6ヶ月(執行猶予4年)+罰金1,000万円 |
| 両法人 | 罰金2,000万円(当時の最高額) |
| 三栄化学工業会長 | 自殺により公訴棄却 |
両社は破産。 だが、環境の回復には10年以上かかった。
🌱第4章:再生への道
2004年から、青森・岩手両県が代執行で撤去作業を開始。 2013年、廃棄物の全量撤去が完了。 その後も地下水の浄化作業は2022年度まで続いた。
地元では、環境学習や植樹活動が行われ、 「二度と同じ過ちを繰り返さない」ための取り組みが始まった。
🧠エピローグ:制度の盲点と“見えない犠牲者”
この事件は、廃棄物処理制度の隙間を突いた“構造的犯罪”だった。 届出制の甘さ、委託の多重構造、監視の限界。 そして、犠牲になったのは――声なき自然と、そこに暮らす人々だった。