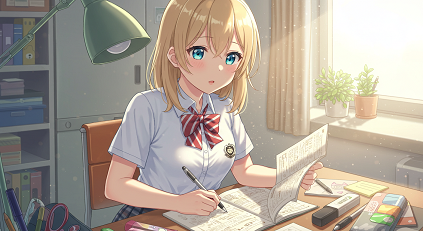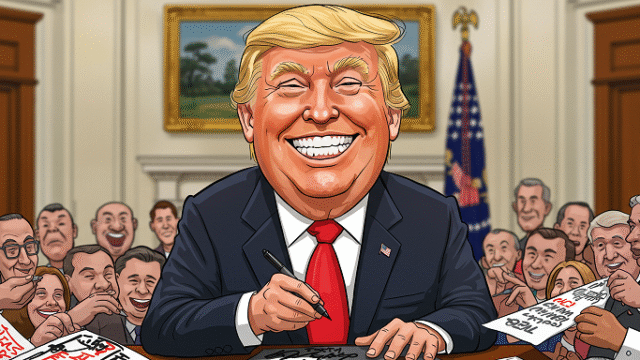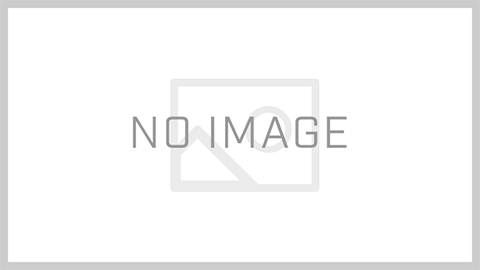🕰️プロローグ:清流のはずが、枯れ川に
新潟県・信濃川。 JR東日本が誇る水力発電所は、年間14億kWhを生み出し、 山手線をはじめとする首都圏の電車を支えていた。
だがその裏で、10年間にわたる違法取水と虚偽報告が行われていた。 川は枯れ、魚は消え、住民は沈黙を強いられた。
⚙️第1章:リミッターという名の改ざん
JR東日本は、信濃川の取水量と放流量を管理する装置に、 “リミッター”と呼ばれるプログラム改ざんを施していた。
- 許可水量を超えて取水しても、記録上は適正値に見える
- 放流量が基準を下回っても、記録上は基準以上に見える
この“頭切り”と呼ばれる手法により、382件の虚偽報告が行われた。
📉第2章:枯れた川、消えた魚
違法取水の影響は深刻だった。
- 宮中取水ダムから小千谷発電所までの約60kmが枯れ川状態
- 地下水の減少、漁業の廃業、サケの遡上激減
- 放流量は毎秒7トンにまで減少(目標は33トン以上)
信濃川は、鉄道の電力のために命を削られていた。
🧠第3章:虚偽報告と行政処分
2008年、情報公開請求により不正が発覚。 2009年2月、国土交通省は「極めて悪質かつ重大な河川法違反」として、 JR東日本の水利権を取り消し、発電を停止させた。
- 超過取水:約1.8億㎥(1998〜2007年)
- 放流不足:約38万㎥
- 無許可工作物:175件
- 虚偽報告:点検要請に対し「適正」と回答
🚉第4章:電車の灯はどうなる?
信濃川発電所は、JR東日本の電力の約4分の1を供給していた。 発電停止により、首都圏の電車運行への影響が懸念されたが、 川崎火力発電所のフル稼働と東京電力からの購入で対応された。
🌱第5章:再開と再生
2010年、JR東日本は水利権を再取得。 放流量は毎秒40〜120トンに増加し、 サケの遡上数は146匹→1514匹へと回復した。
だが、住民の不信は根強く残った。 「信濃川のあるべき姿市民懇談会」が開かれ、 JRへの再発防止策と説明責任が求められた。
🧩エピローグ:流れを止めたのは誰か
この事件は、 「電力のために川を犠牲にしていいのか」 という問いを突きつけた。
- なぜ10年間も虚偽報告が続いたのか?
- なぜ“鉄道会社”が“水利権”を悪用したのか?
- なぜ行政はもっと早く動けなかったのか?
信濃川の流れは、 企業倫理と公共資源の境界を洗い出した。