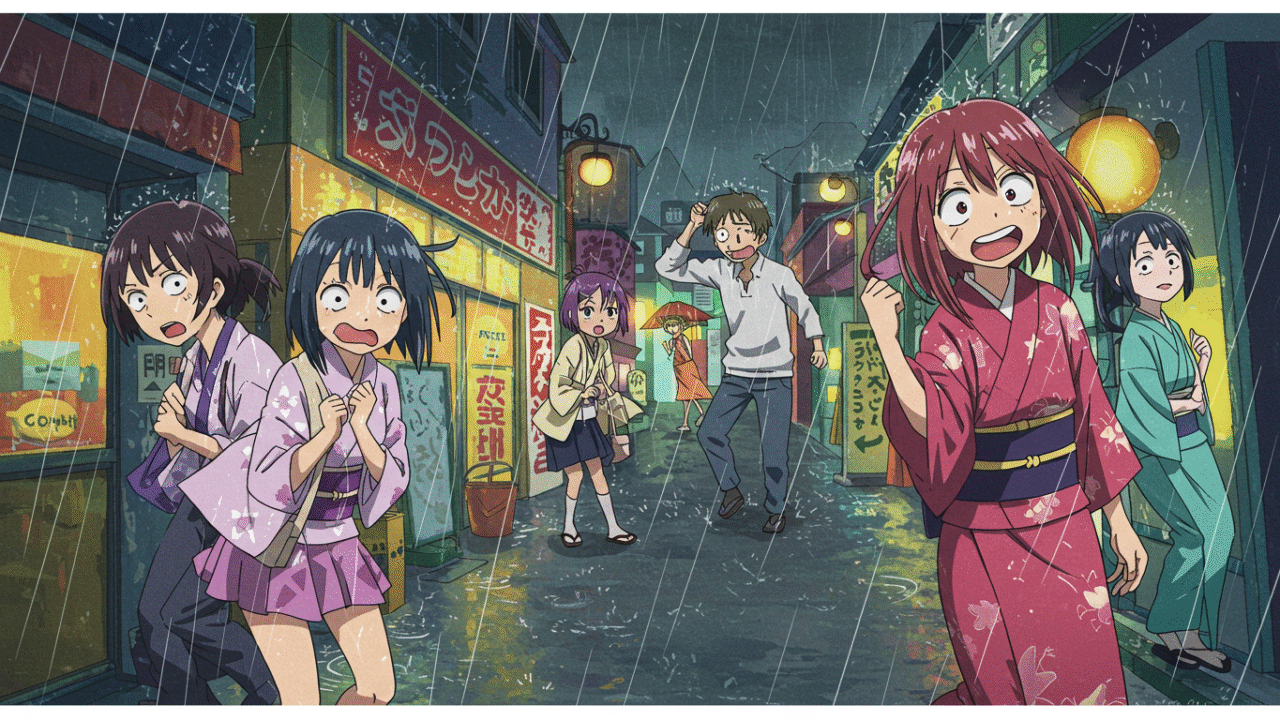2025年8月10日深夜、熊本市中心部は、経験したことのないような記録的な大雨に見舞われました。 その結果、繁華街や住宅街で相次いだ浸水被害。今回の現地調査で明らかになったのは、「内水氾濫」という、あまり知られていない水害のメカニズムでした。

🏙️ 繁華街が水に沈んだ理由
熊本市中央区の下通──アーケード街の一部では、路面が10センチ以上冠水。 この場所、実は周囲よりも標高が2〜3メートルほど低く、くぼ地のような地形になっているそうです。
そこに、200年に1度レベルの豪雨が重なったことで、雨水が一気に集まり、排水が追いつかずに「内水氾濫」が発生。 つまり、川が氾濫したわけではなく、街の中に雨水が溜まってしまったのです。
🧭 ハザードマップは“未来の地図”
山口大学の山本晴彦名誉教授によると、今回の浸水エリアは、熊本市が公表している「内水氾濫の浸水想定区域図」にも含まれていたとのこと。 「排水機能をいくら向上させても、短時間の記録的な大雨には限界がある。だからこそ、地域のリスクを知り、止水板などで備えることが重要」と語っています。
過去の地図を紐解くと、今回の浸水エリアはかつて水田や畑だった場所。水はけが悪く、地形的にもリスクが高かった可能性があるそうです。
🌊 井芹川の急激な増水と住宅街の浸水
繁華街から1キロほど離れた中央区や西区の住宅街でも、床上まで水につかる被害が発生。 近くを流れる井芹川では、10日午後10時に0.36メートルだった水位が、わずか1時間後には3.08メートルに急上昇。 午前1時には「氾濫危険水位」を超え、4.16メートルに達していました。
堤防からの越水と、排水が追いつかない内水氾濫が同時に起きたことで、広範囲にわたって浸水したとみられています。
📹 防犯カメラが捉えた“水の侵入”
下通1丁目の酒屋に設置された防犯カメラには、雨が激しく地面を打ちつける様子、そしてわずか20分でくるぶしまで水が迫る様子が記録されていました。 ゴミ袋が流されるほどの勢い──水害は、静かに、しかし確実に街を飲み込んでいったのです。
🧠 私たちにできること
今回の熊本の事例は、「川が氾濫しなくても街が水に沈む」ことを教えてくれました。 ハザードマップを確認すること。土地の成り立ちを知ること。 そして、止水板や防水シートなど、個人レベルでできる備えをしておくこと。
災害は「いつか」ではなく「いつでも」。 だからこそ、知ることが第一歩なのだと思います。