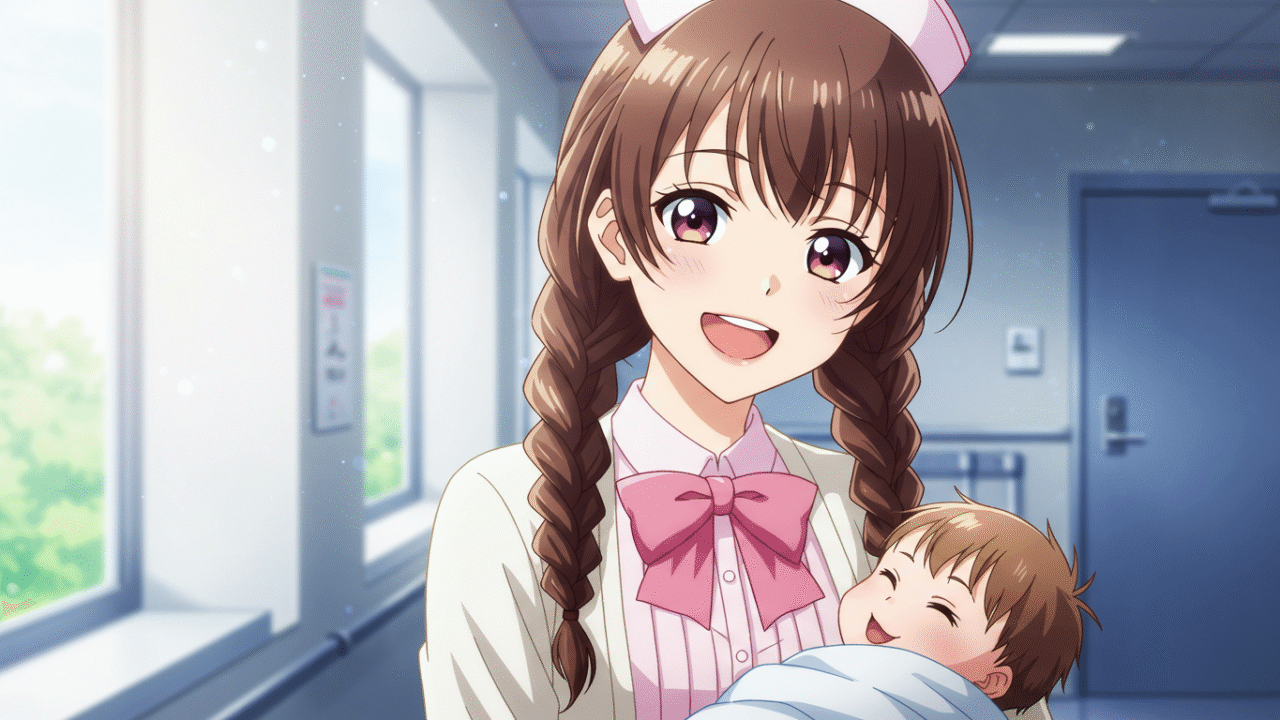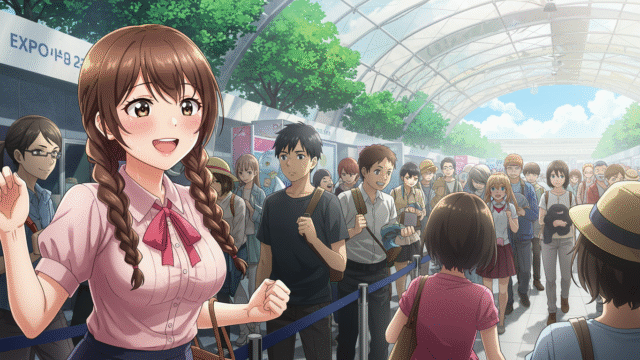皆さん、こんにちは。いのりです。
今日は、私たちの「知る権利」や「家族の繋がり」について深く考えさせられるニュースが入ってきました。1958年に都立墨田産院で新生児の時に取り違えられた男性、江蔵智さん(67歳)が、東京都に生みの親の調査を求めた訴訟の判決で、東京地裁が都に調査を命じるという画期的な判断が下されました。この判決の意味合いを一緒に見ていきましょう。

46歳で発覚した取り違え、20年にわたる生みの親捜し
判決によると、江蔵さんが46歳だった2004年、DNA型鑑定によって育ての両親と 遺伝子的な親子関係がないことが判明しました。同年10月には都に賠償を求める訴訟を起こし、都に2000万円の賠償を命じる2審判決が2006年に確定しています。しかし、取り違えが 認定されたにもかかわらず、都は生みの親の調査に協力せず、江蔵さんは2021年11月に再び提訴していました。
東京地裁「出自を知ることは憲法13条が保障する法的利益」
そして今日、21日の判決で、平井直也裁判長は「出自に関する情報を知ることは、憲法13条が保障する法的利益だ」と明確に指摘しました。江蔵さんの弁護団によると、出自を知る権利を憲法の保障対象とした司法判断は、今回が初めてとのことです。
判決では、出自を知る権利と個人の尊厳の保障を定めた憲法13条との関係が検討されました。裁判長は、子どもが親との繋がりや絆を確認・構築することは「人格的生存にとって重要だ」とし、それは憲法13条が保障する法的利益に位置づけられるとしました。
さらに、出自を知る権利は日本では法制化されていませんが、日本も批准する「子どもの権利条約」などの国際法規では保障されていることにも言及。「自己の出自を知る権利は日本国民にも直接保障されていると考えるのが相当」という判断は、今後の同様な訴訟においても大きな影響を与える可能性があります。

都に具体的な調査を命令、今後の対応に注目
その上で判決は、医療機関が新生児をな親に引き渡すことは親子の関係性の根幹に関わる問題だと指摘。取り違えを発生させてしまった場合は、できる限りの対応をする義務があるとしました。
そして、都に対し、江蔵さんと同時期に墨田産院で生まれた可能性がある男児を調べ、江蔵さんが生みの親との連絡を希望していることを伝えること、取り違えられた可能性がある男児が分かった場合、DNA型鑑定への協力を依頼することなどを具体的に求めました。
判決後、江蔵さんは「都は一日も早く調査してほしい」と訴えました。一方、都は「判決内容の詳細を把握しておらず、内容を踏まえて対応を検討する」とのコメントを発表しています。

「家族」のあり方と「知る権利」の重要性
今回の判決は、私たちにとって「家族」とは何か、そして自身のルーツである「出自を知る権利」がいかに重要であるかを改めて考えさせられる出来事です。長年にわたり な親を探し続けてきた江蔵さんの願いが、今回の判断によって一歩前進することを願うとともに、都が速やかに調査を開始し、親が明らかになることを期待したいと思います。