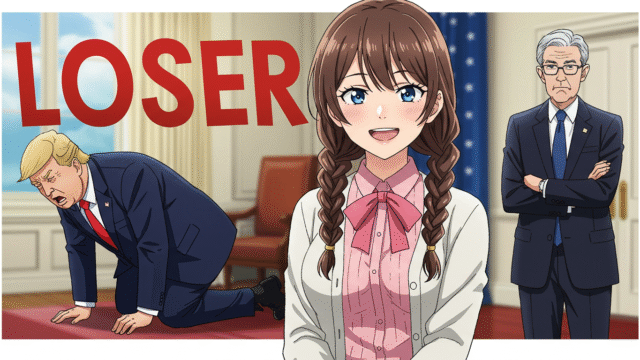4月2日に発表されたトランプ大統領による「相互関税」の詳細。その衝撃は市場の想定を大きく超え、世界同時株安、いわゆる「トランプ関税ショック」を引き起こしました。今、投資家の視線は、この関税が実体経済と企業収益にどのような影響を与えるのか、その見極めに集中しています。
そんな中、アメリカでは今週から、日本でも4月中下旬から主要企業の決算発表シーズンが本格化します。本稿では、日米の決算発表に焦点を当て、株安の連鎖が続く株式市場の今後の行方を深掘りしていきます。
アメリカ主要企業の「業績下振れリスク懸念」が台頭
今週後半から始まるアメリカ主要企業の決算発表。市場予想では、S&P500種指数採用銘柄の2025年1-3月期のEPS(1株当たり利益)は前年比+7%と見込まれています。しかし、前期の+17%から大幅な鈍化は否めません。
さらに懸念されるのは、今後の見通しです。現時点では4-12月期にかけて二桁成長への回復が期待されていますが、
- 年初からの業績見通しがすでに下方修正傾向にある
- 「トランプ相互関税」の規模が想定以上に大きい
これらの要因から、今後の業績にはさらなる下振れリスクが意識されます。特に、4月末から5月初旬に決算発表を控える“マグニフィセントセブン”をはじめとする主要ハイテク株の動向は注視が必要です。
日本株は「企業の減益リスク」を織り込む必要がある
一方、日本企業の決算発表は4月中下旬から本格的にスタートします。4月1日発表の日銀短観では、2025年度の企業収益(全産業・経常利益)計画は前年比-1.4%と、現時点では慎重な見通しとなっています。想定為替レートは1ドル=147.06円と、ほぼ前年度並みです。
しかし、証券系大手調査機関の2025年度経常利益予想は+2.6%とわずかな増益にとどまります。過去の傾向から見ても、企業側の期初予想は保守的になりやすい傾向があります。
今回の「トランプ相互関税」の着地点が見えない状況下での決算発表は、ドル円相場の変動リスクも加わり、輸出企業を中心に2025年度の業績予想が6年ぶりの減益に転じる可能性も考慮しておく必要があります。
日本株が本格的に反転するためには、今後の決算発表で「これ以上業績は悪くならない」という安心感、いわゆるアク抜け感が必要です。当面は、年後半の業績回復期待に対しても、より厳しい見通しが織り込まれる展開が予想され、その目安は主要企業の決算が出揃う5月中旬となりそうです。
「震源地」アメリカ株の底入れに必要な4つの条件
日米の企業業績を見通す上で、やはり「震源地」であるアメリカ市場の動向が重要です。アメリカ株の本格的な底入れには、以下の条件を満たす必要があると考えられます。
- 足元の決算発表でアク抜け感が出ること
- FRB(連邦準備制度理事会)の利下げ時期の前倒しと、利下げ幅の拡大(次回のFOMCは5月6-7日、その後6月17-18日)
- 来年(2026年秋)の中間選挙に向けたアメリカ経済の成長促進策の前倒し発動(規制緩和や大型減税など)
- トランプ大統領の“心変わり”(関税率の修正など)
特に4点目は、スケジュール化できないものの、株価にとってポジティブなサプライズ要因となり得ます。全米規模の反トランプ集会などが、トランプ大統領の政策修正を促す可能性も視野に入れるべきでしょう。今後のトランプ大統領の支持率の推移は、その動向を探る上で重要な指標となります。
過去のショック安局面と比較すると、今回の「トランプ関税ショック」は、市場の予想外の発表による「市場との認識ギャップ」という点で、2024年の「日銀ショック」と類似しています。人為的な要因によるショック安であるならば、今後の対応次第で状況が改善する余地も残されています。
しかし、トランプ大統領の政策転換がない場合、世界的なスタグフレーションのリスクも考慮しておく必要があり、その場合は日本株の本格的な回復には時間を要するでしょう。
「二番底リスク」はあるが中長期での投資チャンスが接近
結論として、日米の株式市場は、「トランプ相互関税」の詳細発表という悪材料がいったん出尽くしとなったとしても、景気と企業収益への影響が完全に織り込まれるまでには時間を要します。そのため、株価が一旦底入れしたとしても、その後に「二番底」を形成するリスクも念頭に置いておくべきでしょう。
しかし、株式市場は過去の幾多のショックを乗り越えてきました。短期的な急落局面では、過度な悲観論に惑わされず、冷静に対処することが重要です。
日本株の本格的な反転には時間を要するかもしれませんが、足元の急落は、売られすぎからの反発や、新NISAを活用した中長期投資のチャンスが近づいているサインと捉えることもできます。
今後の決算発表の内容を注視しつつ、冷静な判断に基づいた投資戦略を検討していくことが求められます。